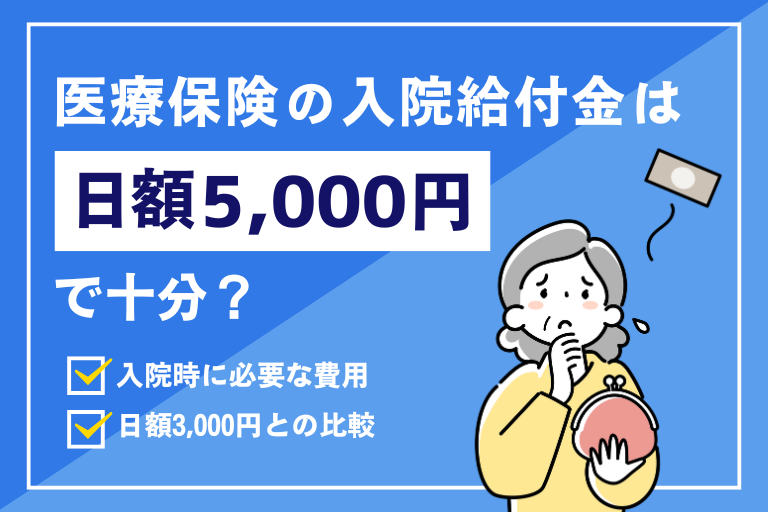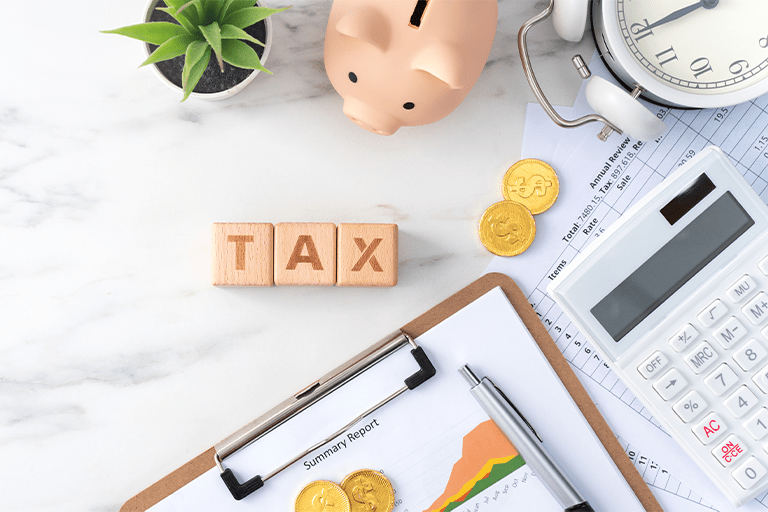
医療保険の給付金は税金がかかる?確定申告が必要かについても解説
医療保険の給付金を受け取る際に「税金はかかるのか」「確定申告は必要か」など、税金に関して不安に感じるている方も多いのではないでしょうか。
医療保険に限らず保険商品は受給内容によって税金がかかる場合も多く「どんなケースで税金がかかるのか」を正しく把握しなければいけません。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、医療保険の税金について解説します。
解約返戻金を受け取る場合の課税関係や医療費控除の申請方法もまとめました。
医療保険の税金が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
医療保険で受け取る給付金に税金はかかる?

医療保険に税金がかかるかは給付内容(主契約の給付金または特約の死亡保障)や受取人など、さまざまな条件で異なります。
病気やケガで生じる医療費負担の軽減を目的にした保険のため、税金がかかるかどうかは、ぜひ押さえておきたいポイントです。
ここでは、医療保険の給付金に税金がかかるのか、また特約部分の課税関係について解説します。
入院・手術給付金であれば税金はかからない
医療保険の入院給付金や手術給付金に税金はかかりません。
医療保険の給付金は「身体の傷害に基因して支払いを受ける保険金」として、非課税扱いとなるためです。
また、医療保険の給付金は非課税のため、受給金額に関わらず確定申告が不要です。
ただし被保険者(保険対象者)が亡くなり、遺族が未請求の入院給付金や手術給付金を受け取る場合は、相続税が課税されるケースもあります。
他にも、被保険者が受け取った給付金を使い切らずに亡くなった場合、残った給付金は相続税の課税対象になるため注意が必要です。
特約の死亡保険は税金がかかる
医療保険に死亡保障特約を付けている場合、被保険者の死亡により遺族が受け取った死亡保険金は課税対象となります。
課税される税金の種類は契約形態によって以下のとおり「相続税」「所得税」「贈与税」と異なります。
【契約形態例と税金の種類】
| 契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 本人 | 配偶者や子供 | 相続税 |
| 本人 | 配偶者や子供 | 本人 | 所得税 |
| 本人 | 配偶者 | 子供 | 贈与税 |
医療保険の死亡保障特約は少額なケースがほとんどです。
しかし、受取人の所得や家族構成などによっては、確定申告が必要なケースもあるため注意が必要です。
満期保険金や解約返戻金を受け取る場合は?

医療保険は保険料掛け捨て型商品のため、満期保険金や中途解約した場合の解約返戻金はありません。
ただし、保険料払済タイプ(※)の契約では、保険料払込完了後に解約すると解約返戻金が支払われるケースもあります。
※一定期間で保険料の払込みが終了する契約
ここでは上記ケースで解約返戻金を受け取る場合の税金について解説します。
契約者=受取人の場合
契約者(保険料負担者)が医療保険の解約返戻金を受け取る場合、一時所得として所得税がかかります。
【一時所得の課税対象額】
一時所得の課税対象額={(受け取った解約返戻金額-払い込んだ保険料)-50万円(一時所得の特別控除額)}× 1/2
例えば解約返戻金額が300万円、払い込んだ保険料が200万円の場合、以下のように計算され、一時所得の課税対象金額は25万円となります。
一時所得の課税対象金額={(300万円-200万円-)-50万円} ×1/2=25万円
契約者≠受取人の場合
契約者(保険料負担者)以外が医療保険の解約返戻金を受け取る場合は、贈与税の課税対象になります。
【贈与税の課税対象金額】
受け取った解約返戻金額(※)-110万円(贈与税の基礎控除額)
※同一年に他に贈与がある場合は合算する
例えば解約返戻金額が300万円で同一年に他の贈与がない場合は、以下のように計算され、贈与税の課税対象金額は190万円となります。
贈与税の課税対象金額=300万円-110万円=190万円
医療保険の税金に関するよくある質問
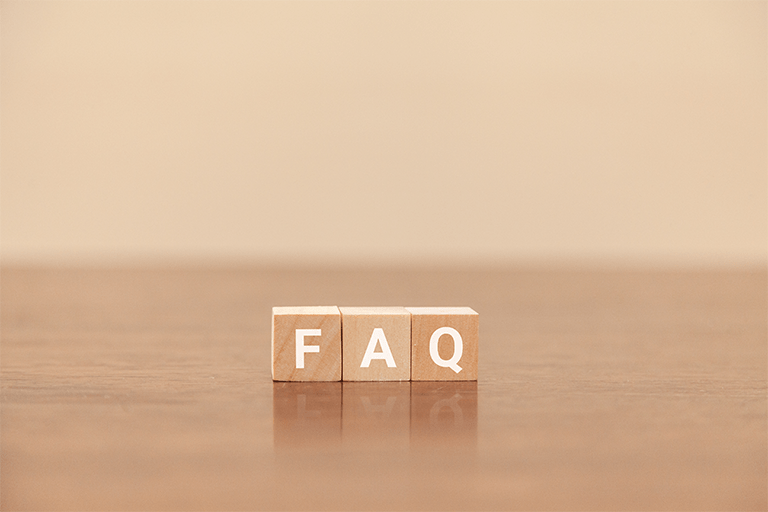
ここでは医療保険の税金に関するよくある質問についてまとめました。
医療保険の給付を受ける方、医療費控除の仕組みや申請方法について知りたい方は参考にしてください。
給付金を受け取ったら確定申告は必要?
医療保険の給付金には税金がかからないため、原則として確定申告は不要です。
ただし被保険者(保険対象者)が亡くなり、遺族が医療保険の給付金を受け取る場合は相続税の申告が必要になるケースもあります。
確定申告が必要かどうかは、預貯金や他の資産など相続財産によって異なるため、不安であれば保険会社や税理士などへ相談すると良いでしょう。
医療保険を給付を受けた場合でも医療費控除を受けられますか?
医療保険の給付を受けた場合でも、1年間に支払った医療費が一定金額を超えるケースは、医療費控除を受けられます。
ただし、医療保険の給付金が実際に支払った医療費を超える場合は、医療費控除の適用を受けられません。
なお、医療費控除の適用を受ける場合は、給与所得者(会社員、パート・アルバイト)であっても確定申告が必要です。
確定申告では医療費の領収書や医療保険の給付金明細が必要となるため、医療費控除申請まで保管しておく必要があります。
そもそも医療費控除って何?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円以上(※)の場合に、所得から一定金額を控除できる制度(所得控除)です。
※総所得金額200万円未満の場合は総所得金額×5%
医療費控除の対象になる医療費の条件は以下のとおりです。
- 本人および生計を共にする親族のために支払った医療費
- 医療費控除を受ける年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費
【医療費控除の計算方法】
医療費控除は以下の計算式で計算されます。
医療費控除額=(1年間に支払った医療費の合計額-医療保険や生命保険で補てんされる金額) – 10万円(※)
※1年間の総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%まで
例えば以下の条件で医療費を支払った場合、年間で20万円の医療費控除が受けられます。
- 1年間に支払った医療費 : 60万円
- 医療保険の受給額 : 30万円
- 総所得金額 : 200万円以上
医療費控除額=(60万円-30万円)-10万円=20万円
具体的にどのような費用が医療費控除の対象ですか?
原則として病気やケガの治療目的で支払った費用は、公的健康保険適用の有無を問わず医療費控除の対象になります。
| 医療費控除対象になる費用の具体例 | |
|---|---|
| 病院に支払う入院 通院費用など | ・外来診療費用や入院費用、手術費用 ・通院にかかった交通費 ・入院時の部屋代や差額ベッド代、入院時の食事代 ・治療に関するリハビリ料金 ・介護・保健施設収容に伴う人的費用 |
| 医薬品・医療器具 | ・処方箋に基づく医薬品購入費用 ・薬局で購入した医薬品(治療を目的とするもの) ・治療に必要なコルセットや松葉杖、義手、義足などの購入費用 |
| 歯科・眼科治療 | ・レーシック手術費用 ・角膜矯正療法の費用 ・歯の治療費用 ・歯列矯正費用(治療目的の場合) |
| 妊娠・出産 | ・妊娠の診断を受けた後の定期検診費用や交通費 ・助産師による分べんの介助費用 ・不妊治療の費用 |
ただし通院費用のうち、タクシー代は公的交通機関が利用できない場合を除き医療費控除の対象になりません。
また、入院時の部屋代も差額ベッド代(自らの希望で個室や少人数の病室に入院する場合の費用)は医療費控除の対象外です。
医療費控除の申請方法は?
医療費控除の申請方法は以下のとおりです。
1年間に支払った医療費の集計を行います。
税務署または国税庁Webサイトから「医療費控除の明細書」を取得して医療費の詳細を記入します。
医療費の領収書を添付する必要はありません。ただし、領収書は5年間保存する必要があります。
以下のとおり医療費控除の計算を行います。
医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額 – 医療保険や生命保険で補てんされる金額 – 10万円(※)
※1年間の総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%まで
「医療費控除の明細書」を添付して確定申告を行います。
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成するか、税務署で申告書を入手して手書き作成します。
記事まとめ

医療保険の入院給付金には、原則として税金がかかりません。
ただし、被保険者が亡くなった場合や解約返戻金が支払われる場合は、相続税や所得税、贈与税の課税対象となるケースがあります。
税金がかかるのか不安な方は、保険会社や加入した保険代理店、税理士などへ相談すると良いでしょう。
本記事をお届けした「保険のぷろ」では、無料で医療保険の見直しや加入相談を承っています。
「加入している医療保険は自分に合っているか」「不足している保障内容は?」などお悩みの方は、ぜひ「保険のぷろ」へご相談ください。