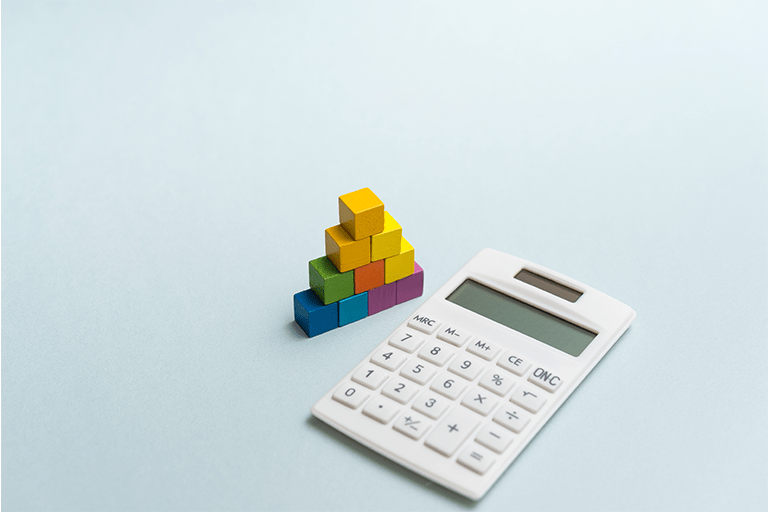差額ベッド代とは?追加費用が発生しないケースや医療控除の対象になるかも解説
怪我や病気で病棟滞在すると、公的保険制度によって、1〜3割負担で処置を受けられます。
公的保険制度が定める一定額を超えた場合でも「高額療養費制度」を利用すれば、処置費が還付されます。
しかし、通常の大人数スペースではなく、独立スペースや条件のよいスペースを利用した際は「差額ベッド代」がかかるため、注意が必要です。
今回は、無料保険相談を行っている「保険のぷろ」が、差額ベッド代とはどのような費用なのか、費用が発生する条件や事例について詳しく解説します。
「差額ベッド代とは?」と疑問を抱いている方は、ぜひ最後までご覧ください。
差額ベッド代とは
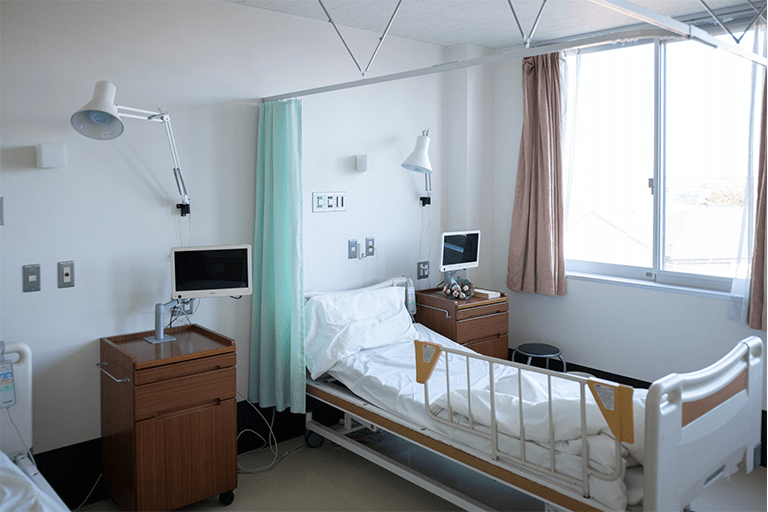
差額ベッド代とは、病棟滞在時に利用するスペースによって別途かかる代金を指します。
基本的に病棟滞在費とは、公的保険や高額療養費制度を利用すれば、大きな自己負担額はかかりません。
しかし、差額ベッド代は、公的保険や高額療養費制度の該当外となり、自己負担額になります。
ここからは、差額ベッド代の概要や相場料金などを解説します。
入院時に利用する部屋によって別途発生する料金のこと
条件のよいスペースを希望して利用した際、病棟滞在費に追加代金がかかりますが、大人数スペースであれば追加代金はかかりません。
大人数スペースであれば追加代金はかかりませんが、条件のよいスペースを希望して利用した際、病棟滞在費に追加代金がかかります。
たとえ4人スペース(小スペース)であっても、差額ベッド代がかかる事例もあるため、注意が必要です。
追加代金が生じるようなスペースは「特別療養環境室」と呼ばれています。
1日あたりの処置費は平均2.1万円ですが、長期間独立スペースに滞在すれば、想像よりも処置費が膨れ上がる可能性に留意しておきましょう。
差額ベッド代の対象となる条件
追加代金の支払い範囲となるスペースの条件とは、以下の通りです。
- 1スペースあたりベッド数が4床以下
- 1人あたりの面積が6.4平方メートル
- ベッドごとのプライバシーが確保されている
- 個人用の収納設備・照明・小机や椅子など個人の所有物を有している
参考:厚生労働省|①「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
上記の条件を全て満たしているスペースに滞在した場合、処置費とは別で追加代金を求められる可能性があります。
ただし、条件に当てはまっていても、追加代金を支払わなくても良い事例もあるため、一概にはいえません。
追加代金の該当にはならない事例は、後ほど詳しく紹介します。
差額ベッド代の相場は?
独立スペースや小スペースを利用した際の相場代金とは、以下の通りです。
| スペースの人数 | 相場代金 |
|---|---|
| 1人 | 8,437円 |
| 2人 | 3,137円 |
| 3人 | 2,808円 |
| 4人 | 2,724円 |
| 合計 | 6,714円 |
※令和5年7月1日時点
2人スペースまでの差は6,000円程度となっていますが、1人スペース(個室)になると代金が倍異なります。
1人スペースを希望すると、4人や3人などの小スペースに比べると、自己負担額が大きくなる点に注意が必要です。
公的保険制度は適用される?
通常の大人数スペースであれば公的保険制度が反映され、1〜3割負担になります、
ただし、独立スペースや小スペースを希望する際は、自己負担になるので注意が必要です。
民間の保険に加入している場合は、差額ベッド代が保障される事例もあります。
民間の医療機関とは、公的保険とは別に、任意で加入する保険です。
商品によって保障内容が異なるため、独立スペースや小スペースを希望する方は、差額ベッド代が保障される保険に加入しておくとよいでしょう。
差額ベッド代がかからない事例

承諾書に署名をしていなかったり、医療機関側の都合で特別スペースに滞在したりした場合は、追加代金の該当とはなりません。
追加代金の該当とはならない、代表的な事例を3つ見ていきましょう。
承諾書に署名をしていない場合
独立スペースや小スペースを利用する際、承諾書に署名していない場合は、追加代金の支払いは必要ありません。
承諾書に署名をしたとしても、以下に当てはまる事例は、追加代金を払わなくてもよい可能性があります。
- 承諾書に関する説明がなかった
- 追加代金が明記されていなかった
病棟滞在する際は、処置に関する承諾書に署名をする機会があります。
承諾書の内容を理解できていないまま署名をするのは控え、不明点は医療機関にしっかりと確認しましょう。
ドクターの判断による場合
処置の都合により独立スペースに滞在する場合も、追加料代金の該当とはなりません。
処置の都合とは、ドクターによる判断のため、一概にはいえませんが、以下のような状態が該当します。
- 救急患者、術後患者等であり、安静を必要とする方
- 免疫力低下により感染症にかかる恐れがある方
- 集中処置の実施が必要な方
- 身体的・精神的苦痛を緩和が必要な終末期の方
- 後天性免疫不全症候群に感染している方
- クロイツフェルトやヤコブ病の方
参考:厚生労働省|Taro-01 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について
上記に該当していない方でも、ドクターの判断によっては独立スペースの滞在が認められる可能性があります。
病棟滞在時に独立スペースへ案内された場合は「ドクターによる判断ですか?」と確認しておきましょう。
医療機関側の都合による場合
医療機関側の都合により、独立スペースや小スペースに滞在した際、追加代金はかかりません。
医療機関側の都合とは、以下のような事例があげられます。
- MRSA等に(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症)感染しており、院内感染を防ぐため独立スペースに滞在させた場合
- 追加代金の該当となるスペース以外が満床だった場合
よくある事例として、大人数スペースが満床で独立スペースや小スペースになる事例です。
もちろん医療機関側の都合のため、追加代金を支払う必要はありません。
しかし、医療機関によっては説明なく、療養とは別で追加代金が上乗せされて求められる事例があります。
大人数スペースが満床で独立スペースに滞在する際は、追加代金がかからないか確認しておきましょう。
差額ベッド代が発生しないと明記している医療機関の場合
医療機関によっては、独立スペースや小スペースを利用しても、差額ベッド代はかからないと明記している事例もあります。
代表的なのは、全日本民医連(民医連)に加入している医療機関です。
追加代金に関する情報をホームページで発信している医療機関も増えています。
独立スペースや小スペースを検討している方は、お住まいの地域の医療機関を調べておくとよいでしょう。
FAQ|よくある質問

ここからは、差額ベッド代についてよくある質問にお答えします。
十分な説明を受けず差額ベッド代の承諾書にサインした場合の対処法は?
医療機関側から十分な説明を受けていないにもかかわらず、承諾書へ署名をしてしまった際は、厚生労働省の地方支部に相談しましょう。
追加代金の承諾書に署名したあとは、地方厚生局に追加代金に関する通知が届きます。
お住まいの地域の地方厚生局に電話し、十分な説明がないまま署名してしまった旨を説明し、承諾書を破棄してもらいましょう。
医療費控除の対象になる?
公的保険制度に該当しない差額ベッド代ですが、医療費控除も該当外のため、注意が必要です。
医療費控除とは、1年間のうち一定額の医療費を支払った際に、一部の税金が還付される制度を指します。
1年間10万円もしくは合計所得金額の5%のいずれか、低い方を超える処置費を支払った場合のみ、控除が反映されます。
ドクターの診断や処置に必要な代金のみ、控除の該当となるのが特徴です。
患者希望で利用した独立スペースや小スペースは、処置に必要な代金とは認められないため、控除の該当とはなりません。
一方で、ドクターの判断で独立スペースを利用する場合は、処置に必要な代金に分類されるため、控除の該当となります。
記事まとめ

病棟滞在時にかかる差額ベッド代とは、独立スペースや小スペースを利用した際に別途かかる代金を指します。
差額ベッド代は、公的保険や高額療養費制度の該当外となり、全て自己負担になります。
患者希望で長期間独立スペースや小スペースに滞在すると、処置費が膨れ上がるため、注意しましょう。
なお、ドクターの判断で独立スペースを利用したり、大人数スペースが満床だったりする場合、追加代金はかかりません。
なかに、本来差額ベッド代がかからないにもかかわらず、代金を上乗せして請求してくる事例もあります。
医療機関都合で独立スペースや小スペースを利用する際は、必ず追加代金がかからないかを確認しておくとよいでしょう。