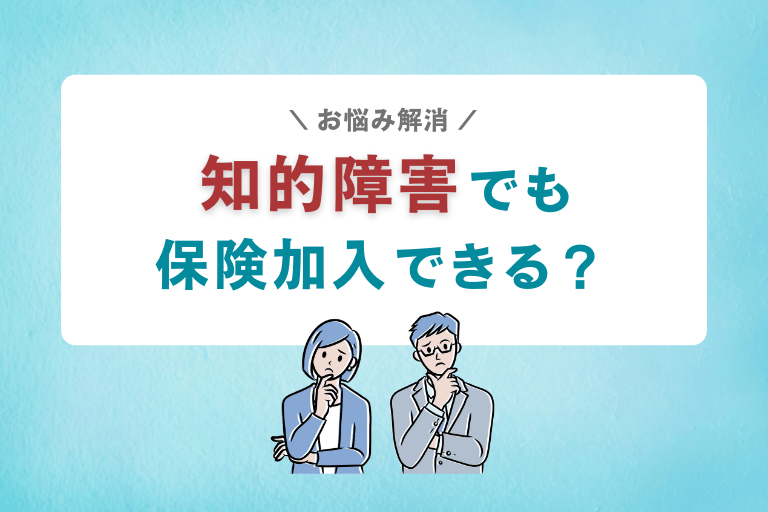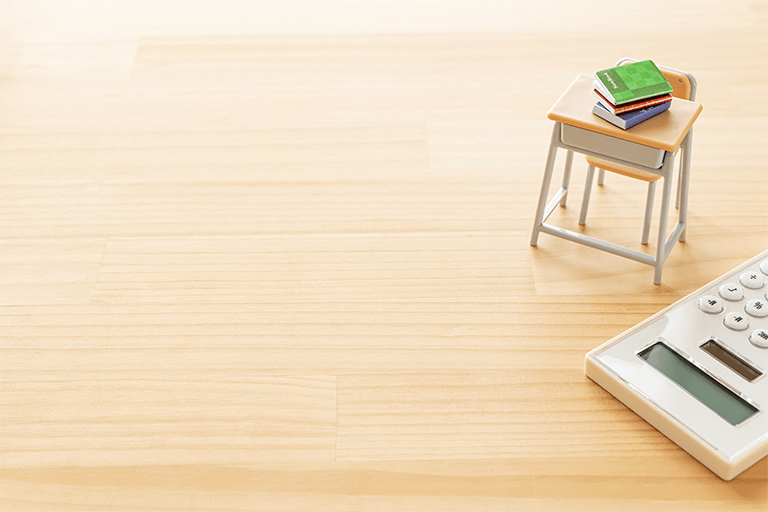妻の死亡保険の必要性は?必要・不要なケースと保険金額の決め方も解説
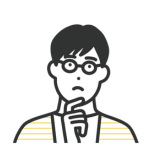
妻の死亡保険に必要性はある?

不要なケースはどんなとき?
妻の死亡保険加入を検討する中で、上記のように必要性を考える方も多いでしょう。
妻の死亡保険は、家族構成や家庭における貯蓄状況、夫の収入などによって必要性が異なります。
本記事では、無料保険相談を行っている「保険のぷろ」が、妻の死亡保険が必要なケースと不要なケースを、具体的に解説します。
死亡保険金額の考え方も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
妻に死亡保険が必要なケース

妻が家計を支えていたり、子どもの教育費を確保したりしたい場合など、家庭の状況によっては、妻にも死亡保険が必要です。
ここでは、妻に死亡保険が必要となる主なケースを紹介します。
自分たちの状況に当てはめながら、備えるべき保障内容を整理してみてください。
経済的に家計を支えている場合
妻がフルタイムやパートなどで働いており、家計の収入源として大きな役割を果たしている場合は、死亡保険が必要と言えます。
妻が亡くなり収入減少に陥ると、家計ひっ迫のリスクが生じます。
共働きで住宅ローンや教育費を支払っている家庭では、毎月の返済や生活費の確保が厳しくなる可能性が高いでしょう。
妻が家計の一部を支えている場合は、生活を守るためにも、死亡保険に加入するのがおすすめです。
専業主婦で家事・育児を担当している場合
妻に死亡保険が必要なケースとして、専業主婦で家事・育児を担っている場合も挙げられます。
専業主婦の妻が亡くなった場合、家事代行サービスや保育サービスなどを利用せざるを得ないでしょう。
外での労働収入はなくても、専業主婦が家庭内で果たす役割は重要です。
小さな子どもを抱え、夫1人がすべて担うとなれば、背負う負担が重くなるのは明確です。
家事・育児の負担が軽減できるよう、死亡保険に加入して備えておくとよいでしょう。
子どもの教育費を確保したい場合
子どもの教育費を確保したい場合も、妻の死亡保険を検討するのがおすすめです。
子どもがまだ小さい場合、将来かかる教育費は大きな負担となります。
妻が亡くなった際に、子育てと家計の両方を夫だけで担うとなれば、子どもの進学や塾代などに影響が出る可能性もゼロではありません。
教育や進路の選択肢を減らさないためにも、教育資金の備えとして妻に死亡保険をかけておくのは有効です。
妻に死亡保険が不要なケース

すべての家庭で妻に死亡保険が必要とは限らず、生活環境や家族構成、経済状況によっては、保険をかけなくても問題がない場合もあります。
次は、妻に死亡保険が不要と考えられる代表的な4つのケースを紹介します。
無駄な保険料を払わないためにも、ぜひ参考にしてください。
子どもがすでに独立している場合
妻に死亡保険が不要なのは、子どもが成人し、すでに独立している場合です。
教育費の出費がなくなると、夫だけで生活を回していけるケースが多く、死亡保険の必要性は低くなるのが大半です。
子どもが就職し自分で生活費を賄っている状態であれば、夫婦2人だけの生活になり、生活費そのものも下がる可能性もあります。
万が一妻に何かあっても、夫の収入があれば家計の急変は少ないと言えます。
子どもが独立している場合は保険加入せず、自分たちで老後資金や生活費の貯金をするとよいでしょう。
夫の収入が安定し、十分に生活できる場合
夫の収入が安定し、十分な生活費が確保できる場合も、妻の死亡保険は不要です。
もしものときでも、夫だけの収入で生活が成り立つからです。
死亡保険の加入を見送るか迷う際は、毎月どのくらいの生活費がかかっているのか、計算してみましょう。
ただし、家事代行サービスや保育サービスを利用する場合は、これまでの生活費に利用料をプラスして考えるのが大切です。
貯蓄や資産が十分にある場合
妻の死亡保険は、家計に十分な貯蓄や資産がある家庭では、必ずしも加入が必要とは限りません。
以下のような経済的な備えがすでに整っている場合は、死亡保険に頼らずとも生活が維持できる可能性は高いでしょう。
- 教育費や今後の生活費を補える貯蓄がある
- 退職金や年金が見込める
- 持ち家があり、住宅ローンや家賃の返済がない
生活の土台を支える貯蓄や資産があれば、妻の死亡によって生活が大きく変わるリスクは小さいと言えます。
死亡保険の加入前に、家計の資産状況を見直して、本当に保障が必要か確認してみましょう。
連生保険に加入している場合
妻の死亡保険が不要になるのは、連生保険に加入している場合です。
連生保険とは、夫婦のうちどちらかが亡くなったとき、一度だけ保険金を受け取れる保険を指します。
連生保険に加入していれば、妻の死亡時に保険金を受け取れる仕組みは整っているので、個別の保険へ入ると保障が重複してしまいます。
無駄な保険料を払う事態になるのは、経済的な負担を抑えるためにも避けるのが得策です。
連生保険の保険金に不足がある場合も、追加で死亡保険に入るより、保障内容の見直しを優先しましょう。
いくら必要?死亡保険金の考え方

少なすぎる保険金は、もしものときに家族が生活に困る可能性があり、逆に高すぎると保険料の負担は大きくなります。
大切なのは、自分の家庭に合った保険金額の見極めです。
無理のない保険設計をするためにも、必要な金額の考え方をしっかり押さえておきましょう。
死亡保険金額の平均について
2024年に実施された、生命保険文化センターの調査によると、死亡保険の平均保険金額は1,936万円です。
なお、世帯主と配偶者では、以下のような結果が出ています。
| 世帯主 | 1,258万円 |
|---|---|
| 配偶者 | 691万円 |
出典:公益財団法人 生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」
https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r6/2024honshiall.pdf
世帯主は男性の比率が85.6%なため、配偶者のほとんどは女性です。
出典:労働調査協議会「統計からみた『家族』の変化」
https://www.rochokyo.gr.jp/articles/2209_7.pdf?utm_source=chatgpt.com
配偶者における平均保険金額は691万円と、世帯主の半分程度という結果からも、多額の保険金は求められていないのがわかります。
ただし、保険金は家族構成や生活スタイルによって異なるため、平均額はあくまで目安として考えましょう。
子ども1人につき2,000万~3,000万円を目安とする
小さなお子さんがいる家庭は、2,000万~3,000万円を目安にするのがおすすめです。
通常、子ども1人にかかる教育費は幼稚園から大学までトータルで1,000万~2,500万円と言われています。
生活費も含めて考えると、子ども1人につき2,000万~3,000万円を死亡保険でカバーするのが理想的です。
もちろん、貯蓄や資産があれば、2,000万円以下の保険金でも十分でしょう。
家計の負担を少なくするためにも、過不足ないプランを心がけるのが重要です。
収入保障保険についても検討してみる
保険料を抑えつつ、万が一の備えをしっかりしたい方は、収入保障保険も選択肢の1つとして検討してみましょう。
収入保障保険は、被保険者が亡くなったときに、遺された家族に毎月一定額が支払われるタイプの保険です。
一括で大きな金額が支払われる死亡保険とは違い、月々の生活費を補う形で支給されるのが特徴です。
保険料が安い一方で、契約から保障開始まで年の数が長くなるほど、保険金総額は減少する点に留意しましょう。
記事まとめ

妻の死亡保険は、必ずしも必要ではありません。
貯蓄や資産が十分にある方や夫の収入が安定している場合は、不要と判断できます。
一方で、妻が家計を支えていたり小さな子どもがいたりするケースでは、死亡保険に加入していないと経済的に困る可能性もあります。
家庭の貯蓄状況や家族構成などを考慮して、必要性を見極めるのが重要です。
安い保険料の死亡保険を探している方には、収入保障保険がおすすめです。
毎月一定の保険金を受け取れ、収入面の安定性が得られるうえ、保険料も割安に設定されています。
本記事を参考に、妻の死亡保険加入を検討してみてください。