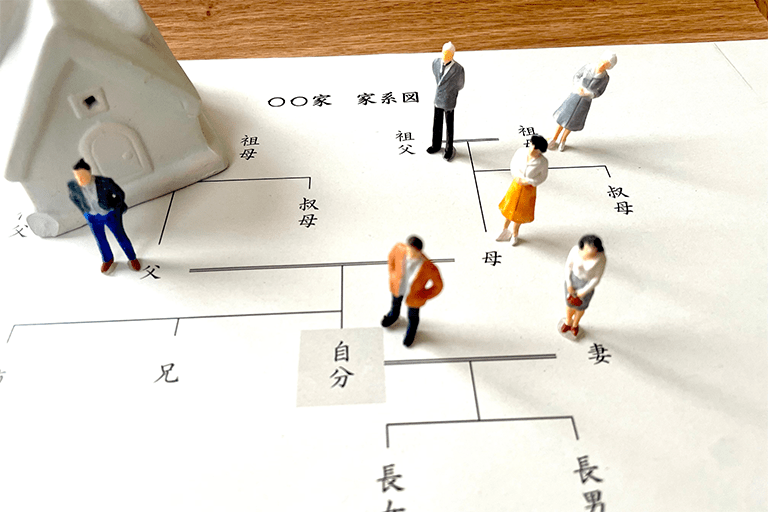
生命保険は相続対策に利用できる?活用するメリットや注意点について解説
生命保険へ加入する際「相続対策になるのか」「どれくらい税負担を減らせるのか」と疑問に感じるている方も多いのではないでしょうか。
生命保険は相続対策に活用できるものの、契約の仕方によっては相続税を減らせない場合があるため、正しく仕組みを把握しなければいけません。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、生命保険を活用した相続対策について解説していきます。
これから生命保険に加入する方や相続対策で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
まずは相続税の対象になる生命保険金について理解しよう
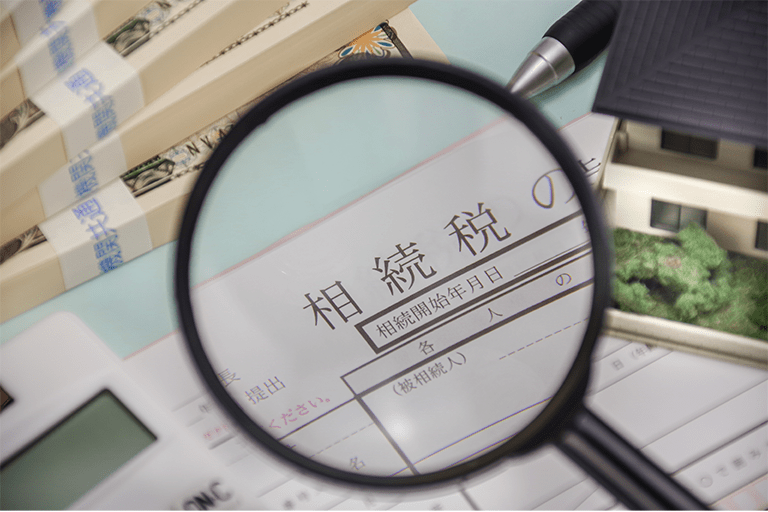
生命保険は保険料負担者と保険金受取人の組み合わせによって、かかる税金が「相続税」「所得税」「贈与税」と異なります。
また税金の種類で税率や納税者が変わるため、加入する生命保険の内容に注意が必要です。
ここでは、どのような契約内容の生命保険が相続税の対象になるのか、保険料を負担する方によって異なる税金の違いについて解説します。
亡くなった方が生命保険の保険料を支払っていたら「相続税」の対象
生命保険金は、亡くなった方が保険料を支払っていたケースの場合、相続税の課税対象となります。
「保険料負担者=被保険者(保険対象者)」の場合、遺族が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産(※)」として相続財産に加算されるためです。
※被相続人(亡くなった方)の死亡により生ずる財産
ただし遺族が生命保険金を受け取った方に、必ず相続税が課せられるわけではありません。
相続税は、生命保険金を含めた相続財産の合計額が基礎控除額を上回る場合にのみかかります。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
出典 : 国税庁 相続税の計算
例えば亡くなった方に配偶者と2人の子どもがいるケースでは、相続財産が基礎控除額の4,800万円を超えない限り相続税がかかりません。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
また生命保険金には非課税枠が設けられているため、法定相続人数によって一定額が相続財産から控除されます。
保険料負担者と保険金受取人によってかかる税金が異なる
生命保険金は、保険料負担者と保険金受取人の組み合わせにより、相続税ではなく所得税または贈与税がかかるケースもあります。
被保険者(保険の対象者)以外が保険料を負担した場合、受け取った保険金は所得または贈与財産とみなされるためです。
課税される税金の種類は、保険料負担者と保険金受取人によって以下のとおり異なります。
【課税される税金の種類】
| 契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | 相続税 |
| B | A | B | 所得税 |
| C | A | B | 贈与税 |
出典 : 国税庁 死亡保険金を受け取ったとき
例えば、夫が保険料を負担して妻を被保険者とした生命保険に加入している場合、夫が保険金を受け取ると課せられる税金は所得税です。
一方、妻を被保険者とした生命保険で夫が保険料を負担し、子どもが保険金を受け取るケースでは贈与税の対象となります。
生命保険は契約形態により課せられる税金や税率が異なるため、保険料負担者・被保険者・保険金受取人の組み合わせを慎重に判断する必要があります。
生命保険を相続対策として活用する5つのメリット

生命保険は万が一の保障だけでなく、相続税の節税や相続人間のトラブル防止など相続対策として活用できます。
生命保険へ加入する際は保有資産や相続人の状況から、相続対策としてどのようなメリットがあるのか把握しておくと良いでしょう。
ここでは、生命保険を相続対策として活用する5つのメリットを解説します。
保険金の非課税枠を利用して税負担を軽減できる
生命保険は保険金の非課税枠を利用して、相続税の税負担を軽減できます。
相続人が保険金を受け取った場合、下記の金額が非課税扱いとなるためです。
生命保険の非課税枠=500万円 × 法定相続人数
出典 : 国税庁 相続税の課税対象になる死亡保険金
例えば法定相続人が4人で3,000万円の保険金を受け取るケースでは、2,000万円が非課税扱いとなります。
生命保険の非課税枠=500万円 × 4人=2,000万円
ただし、法定相続人以外の者が保険金を受け取った場合、非課税枠の適用が受けられません。
また、相続を放棄した者や内縁関係の者が受け取った保険金も、非課税扱いとならないため注意が必要です。
特定の人に確実に遺産を残せる
生命保険を相続対策として活用すれば、遺言書の作成や特別な手続きを行わずに特定の人へ遺産を残せます。
生命保険は契約時に受取人を指定可能で、保険金は受取人固有の財産とみなされるためです。
預金や株式、不動産など他の資産は、相続人全員で「誰がどの資産を受け取るか」を話し合う遺産分割協議を行ったうえで決めなければいけません。
生命保険は受取人が決まっているため、遺産分割協議の必要がなく、スムーズに相続手続きが可能です。
また受取人が指定されているため、相続人同士の争いやトラブルが起きない点も、生命保険を相続対策として活用するメリットと言えます。
まとまった金額を現金で受け取ることができる
生命保険は少ない保険料負担で、高額な保障を得られます。
万が一の場合に遺族へまとまった現金を残せる点は、生命保険を相続対策として活用するメリットの1つです。
特に以下の方は、多大な経済負担が生じるケースもあるため、生命保険による保障は大きな安心につながります。
- 預貯金額が少ない方
- 子育て世代の方
- 住宅ローンを抱える方
- 夫婦どちらかの収入のみで生計を立てている方
また、保険期間を定めた定期タイプの生命保険であれば「退職するまで」「子どもが独立する年齢まで」など、特定の期間だけ保障を厚くできます。
ライフプランに合わせて保障額を設定できる点も、生命保険を相続対策に活用するメリットと言えるでしょう。
相続放棄した場合でも保険金を受け取れる
特定の者を生命保険の受取人に指定しておけば、指定された者が相続を放棄した場合でも保険金を受け取れます。
例えば以下の理由で相続放棄するケースでも、まとまった資産を渡せるのは生命保険を相続対策に活用するメリットと言えるでしょう。
- マイナスの財産(借金)が多い
- 被相続人(亡くなった者)が借金の連帯保証人になっていた
- 自分以外の親族に相続財産を与えたい
ただし相続を放棄した者が保険金を受け取る場合、生命保険金の非課税枠(※)は利用できません。
※法定相続人が保険金を受け取る場合「500万円×法定相続人数」の額が非課税扱いになる
また相続を放棄するには、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
相続開始から3ヶ月以内に申し立てを行わないと、マイナス財産を含めてすべての財産を相続する「単純承認」をしたとみなされるため注意が必要です。
代償分割に活用できる
生命保険は相続対策の1つとして、代償分割に活用できます。
代償分割とは、特定の相続人に財産を取得させ、他の相続人へ代わりの金銭(代償金)を支払う遺産分割方法です。
- 相続人 : 被相続人の子どもが3名(A・B・C )
- 相続財産 : 6,000万円の自宅マンション
- 自宅マンションはAが取得する
上記ケースではBとCへ公平に財産を取得させるため、以下のとおり生命保険を活用する代償分割が考えられます。
- Aを受取人とした保険金4,000万円の生命保険を契約する
- 相続発生時にAが生命保険金でBとCへ2,000万円ずつ代償金を支払う
代償分割は財産を分割させる必要がないため、不動産や自社株など分割しにくい資産の相続に有効です。
しかし、代償金を多く支払ってしまった場合は贈与税が課される可能性もあります。

生命保険を代償分割に活用したい方は、資産額を正しく評価し、代償金の設定を慎重に行う必要があるでしょう。
記事まとめ
生命保険は相続税の非課税枠を利用できるほか、特定の者を保険金の受取人に指定できるため相続対策に活用できます。
ただし保険料負担者や保険金受取人の組み合わせによって、かかる税金や税率が異なる点に注意が必要です。
税金面で不安や疑問があれば保険会社や保険代理店、税理士などへ相談すると良いでしょう。
本記事をお届けした「保険のぷろ」では、無料で生命保険の加入相談を承っています。
生命保険を活用した相続対策を検討している方は、ぜひ「保険のぷろ」へご相談ください。








