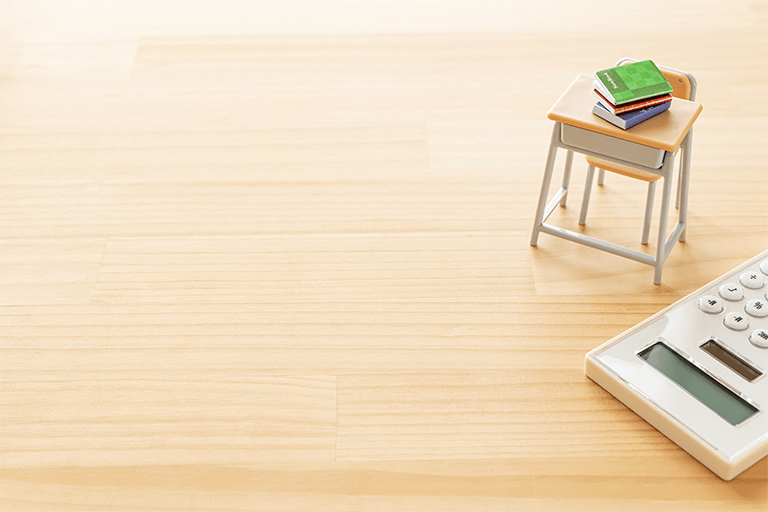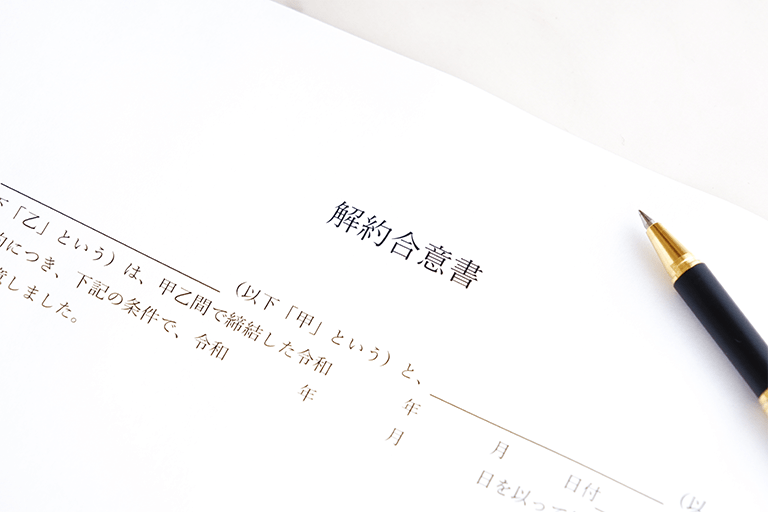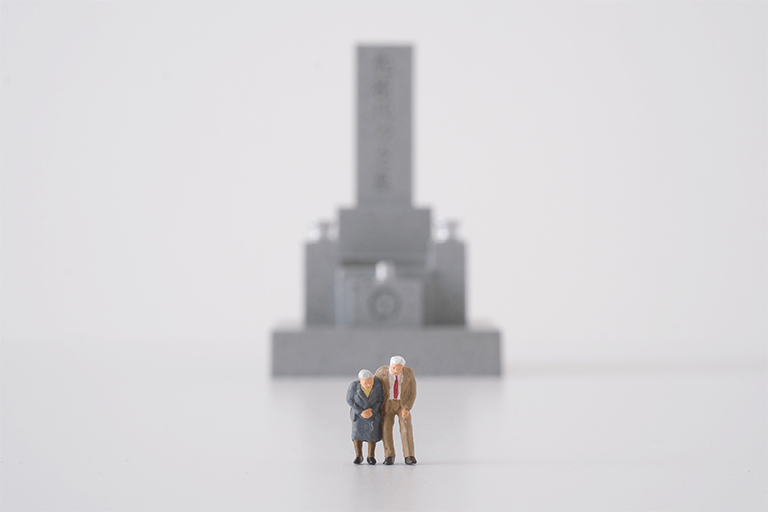
終身保険の必要性について考えてみよう!誰が・どんな目的で加入すべきなの?
「将来のために備えたいけど、終身保険は本当に必要なの?」「保険料を払い続ける価値はある?」と悩む方も多いでしょう。
終身保険は一生涯の保障がある反面、保険料が高く、向いている人・向いていない人がはっきり分かれる保険です。
では、終身保険が必要なのはどんな人なのでしょうか?そもそも生命保険に加入すべきなのでしょうか?
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、生命保険に加入すべきなのか、「いらない」という意見がある理由を踏まえた上で、終身保険の必要性が高い人・低い人のそれぞれの特徴をご紹介します。
後悔しない選択をするためにも、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも生命保険って必要なの?

生命保険は、もしもの時の経済的リスクを減らすための手段です。自分や家族の将来に不安がある方の多くが検討すると思いますが、中には「そもそも生命保険が必要なのか」と疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。
ここでは、終身保険の必要性を考える前に、生命保険の加入率や不要と言われる意見について詳しく解説します。
世の中の約8割が生命保険へ加入している
生命保険文化センター「2022年度 生活保障に関する調査」によれば、生命保険への加入率は、男性が77.6%、女性では81.5%でした。
年齢別に見ると、20代の加入率は全体の約半数ですが、年齢が上がるごとに加入率が増加し、男女ともに50代が最も高い加入率となっています。
また、全年代を通じて女性の方が加入率が高いです。これは、女性特有の病気や妊娠・出産に備えるため、多くの女性が加入しているということが考えられます。
いらないという意見があるのはなぜ?
生命保険を検討している中で、「いらない・不要だ」という意見を耳にしたことはありませんか?
約8割の人が加入しているのにも関わらず、このような意見があるのはなぜなのでしょうか。
以下では、「生命保険はいらない」と言われる主な3つの理由について解説します。
理由①国からの保障制度が整っている
生命保険がいらないと考えられる大きな理由として、公的保障制度が整っていることが挙げられます。
日本は国民皆保険制度を導入しており、全国民が何らかの公的医療保険への加入が義務付けられています。
公的医療保険に加入することによって、病気やケガで医療費が発生しても、原則3割の自己負担で高度な日本の医療機関を受診することができるのです。さらに、1ヶ月の医療費が一定の額を超えた場合、高額療養費制度が利用可能なため、家計への負担を軽減することもできます。
また、日本には公的年金制度もあり、遺族年金を受け取れる場合があるため、万が一配偶者が死亡または高度障害状態になった時でも、国から保障を受けることができるのです。
理由②貯金があれば生命保険に加入する必要がない
生命保険の主な目的は、以下の2点です。
- 万が一の時に残された家族が生活に困らないようにすること
- 病気やケガで働けなくなった時の経済的リスクをカバーすること
すでに貯金が十分にあればこれらの費用を賄うことができるため、生命保険に加入して保険金や給付金を受け取る必要がありません。
そのため、生命保険の必要性が低く、いらないと言われています。
理由③保険を利用する機会が少ない
保険を利用する機会が少ないのも、生命保険が不要だと考えられる理由の一つです。
生命保険は、病気やケガ、死亡などの万が一の事態に備えるものですが、健康に生活することができていれば、保険金や給付金を受け取る機会はほとんどありません。
そのため、「毎月の保険料を払い続けているのに、使わないからもったいない」と感じる人もいるでしょう。
ただし、生命保険を無駄と考えるのではなく、万が一のリスクに備えるものという側面を重視し、必要に応じて加入を検討することが大切です。
終身保険の必要性が高い人

では、どのような人が終身保険に加入すべきなのでしょうか。
ここでは、終身保険の必要性が高い人の特徴について解説します。
- 守るべき家族がいる人
- 十分な貯金ができていない人
- 自営業やフリーランスなど、公的保障が薄い人
- 資産形成を考えている人
- 相続税対策を考えている人
守るべき家族がいる人
まず第一に、守るべき家族(配偶者や子どもなど)がいる人は終身保険の必要性が高いです。
自分が一家の大黒柱として家計を支えていた場合、自分に万が一のことがあった時には残された家族の生活が苦しくなってしまいます。
配偶者が専業主婦(主夫)である場合、収入を補うための資金が必要になり、パートや自営業などの安定した収入がない場合にも、万が一の時の保証は重要です。
子どもがまだ幼いのであれば、それなりの教育費も確保しなければなりません。
そのため、万が一のときに残された家族の生活を支える手段として、終身保険が有効なのです。
十分な貯金ができていない人
万が一の時に備えて、十分な貯金ができていない人も終身保険の必要性が高いです。
日本には公的保障が充実していますが、それでも万が一の時に残された家族の生活費や医療費の自己負担がゼロになるわけではありません。
そのため、収入が不安定・貯蓄状況に不安がある人は、終身保険に加入することが将来への安心材料になるでしょう。
自営業やフリーランスなど、公的保障が薄い人
自営業やフリーランスの方が加入する公的医療保険や公的年金は、会社員や公務員などが加入するものよりも保障が少し薄いです。
具体的に言えば、会社員や公務員などが加入する公的医療保険には、病気やケガで会社を休んだ時に「傷病手当金」が支給されますが、自営業やフリーランスの方が加入する公的医療保険にはこのような仕組みがありません。
また、加入する公的年金にも違いがあり、自営業やフリーランスの方は原則国民年金保険のみの加入です。厚生年金保険には加入せず、遺族年金や障害年金の支給額も少なくなる可能性があります。
そのため、終身保険で万が一に備える必要性が高いのです。
資産形成を考えている人
終身保険は、一生涯の死亡保障を備えながら貯蓄性も兼ね備えるため、返戻率が高く、保障が不要な時期になったら解約をすることで、解約返戻金を受け取ることができます。
「老後に向けて貯金をしたいけれど、なかなか貯められない」という方は、終身保険を活用することで、計画的に資産形成することが可能です。
このように、万が一の時の備えだけでなく、貯蓄性を重視して資産形成がしたい方にも、終身保険の必要性が高いと言えます。
相続税対策を考えている人
終身保険の死亡保険金は相続税対策にも有効なため、相続税の負担を抑えたいと考えている人にもおすすめです。
なぜ相続税対策に有効なのかというと、終身保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税枠として設定されています。そのため、この範囲内で保険金額を設定すれば、相続税が発生せず、全額受け取ることができるのです。
また、終身保険は死亡保険金の受取人を指定することができるため、特定の人物に遺産を残したいという方にとっては有効的な手段と言えるでしょう。
終身保険の必要性が低い人

反対に、終身保険の必要性が低い人の特徴について解説します。
- 独身の人
- 十分な貯金や資産がある人
- 他に合理的な運用手段を持っている人
独身の人
終身保険に加入する大きな目的は「残された家族の生活費や自分の葬儀費用を確保すること」です。
しかし、独身の人は扶養すべき家族がいないため、終身保険の優先度は低くなります。
病気やケガをした時の生活費や医療費は就業不能保険や医療保険で備えたり、貯蓄をしておけば対処することができます。
ただ、独身の人の中でも、将来パートナーと結婚する予定がある人は若いうちに加入し、安い保険料で一生涯の保障を手にするのもおすすめです。
十分な貯金や資産がある人
自分に万が一のことがあっても、残された家族の生活費や自分の葬儀代を賄えるだけの貯蓄がある人は、終身保険の必要性が低いです。
具体的にどのぐらいの貯蓄があれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか。

以下で自分と妻、幼い子どもがいる家族のケースで考えてみましょう。
厚生労働省の「家計調査(2022年)」によると、夫である自分が亡くなった場合の、二人世帯の生活費は平均で月に255,318円かかるようです。1年間では300万円を超えるお金が必要になります。
さらに子どもの入学費や学費が発生し、幼稚園から大学まで全て公立に通った場合でも、1年間で約49万円の教育費を用意しなければなりません。
また、いい葬儀の「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」によると、葬儀費用の総額は、平均で118.5万円かかるようです。
このような場合、葬儀費用に加えて、最低でも5~10年分の貯蓄があると安心できます。
上記のケースでは、1,619万~3,119万円の貯金があれば、終身保険は不要だと考えて良いでしょう。
他に合理的な運用手段を持っている人
投資信託や新NISA、iDeCoなどを活用し、自分で資産運用ができる人も終身保険の必要性は低いです。
終身保険は貯蓄性があり、将来の資産形成に役立ちますが、運用効率は決して高くありません。
そのため、投資や資産運用でより高いリータンを得られる場合や、不動産・株式などの別の資産形成の手段がある場合は、終身保険の貯蓄機能に頼る必要が少なくなります。
自分で判断できない場合はプロに相談しよう

終身保険の必要性は、ライフプランや家族構成、加入している社会保険制度などによって異なります。
「周りがいらないと言ってるから、自分にも終身保険は必要ない」とすぐに判断せず、自分が亡くなった場合にどのようなリスクがあるのか、将来に向けてどのように資産形成をしていくのかをよく考えましょう。
自分で考えるのが難しい、専門家などに判断してもらいたいという方は、保険のぷろの無料相談をご利用ください。
ご自身や家族の収支状況や将来設計などをしっかりとヒアリングした上で、最適な保険プランをご提案いたします。
35社以上の保険商品を取り扱っているため、終身保険よりも他の保険で備えた方がいいという方にも、別途ご案内が可能です。もちろん話を聞くだけでもOKですので、お気軽にご相談ください!