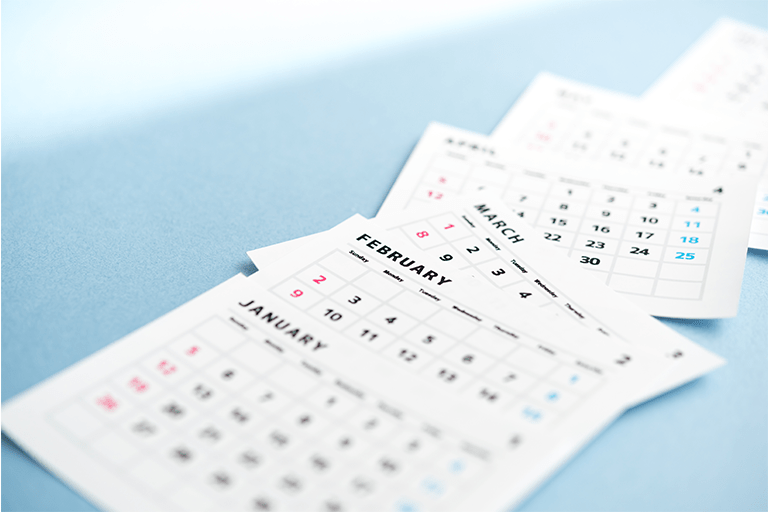新卒社会人は生命保険がいらないのか、加入状況や検討するべき保険の選び方を解説
新卒で社会人になったばかりの20代にとって、生命保険はいらないのでしょうか。
「若いからいらない」と言われる場合が多い中、将来に備えるなら実際の加入率や、加入するメリット・デメリットを理解しておく必要があるでしょう。
今回は、無料保険相談を行っている「保険のぷろ」が、新卒社会人は生命保険がいらないのかを解説します。
生命保険を検討する際に知っておきたいポイントや、必要性の高い保険・不要な保険の見極め方、保険選び方を分かりやすく紹介しています。
新卒社会人にとって生命保険はいらないのかと疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
新卒社会人に生命保険はいらない?20代の加入状況と必要性

新卒で働き始めたばかりの20代にとって、生命保険の必要性は判断が難しいものです。
まずは同世代の加入状況や「いらない」と言われる理由を確認してみましょう。
20代前半の生命保険加入率はどれくらい?
民間の生命保険加入率は20代男性で46.4%、20代女性は57.1%と、すでに一定数が加入しているのがわかります。
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 46.4% | 81.5% | 86.1% | 86.9% |
| 女性 | 57.1% | 82.8% | 86.3% | 87.8% |
ただし、30代以降だと男女ともに加入率は80%を超えており、20代の加入率はまだ低い水準にあります。
参考:生命保険文化センター「第Ⅵ章|生命保険の加入状況」
https://www.jili.or.jp/research/chousa/8944.html
なぜ「いらない」と言われるのか
新卒社会人に生命保険がいらないと言われる理由は、公的保険や勤務先の福利厚生によって十分な保障を受けられるケースが多いためです。
健康保険や厚生年金など公的制度に加えて、企業によっては死亡時の給付金や医療保障が設けられている場合もあります。
たとえば、大手企業では入院費の補助や遺族への一時金制度が整備されているケースも少なくありません。
貯蓄と勤務先の保障で万が一に備えられるなら、民間の生命保険はいらないと考えられるでしょう。
ただし、福利厚生が限定的な場合や、十分な貯蓄がない状況では、民間の生命保険を活用すると安心につながる可能性もあります。
新卒社会人が生命保険に入るメリット

新卒社会人があえて生命保険に加入する場合、月々の保険料が節約できたり貯蓄の少なさをカバーできたりするメリットがあります。
「新卒社会人は生命保険がいらない」「若いからまだ大丈夫」と考える前に、若い世代だからこそ得られる具体的な利点を見ていきましょう。
月々の保険料を節約できる
生命保険の保険料は加入する年齢で決まるため、一般的に若いうちに契約した方が月々の支払額を抑えられます。
さらに、早期で加入すれば、長期的に見たときの支払総額を抑えられる可能性もあるのです。
終身払いの保険は20代と30代で、80歳時点の支払総額に差が生じやすい傾向があります。
つまり若くして加入した方が、支払う保険料の総額の負担は軽くなるケースが多いのです。
同じくらいの保険料を払うのであれば、早い段階から保障を確保できる点は大きなメリットです。
貯蓄が少ないリスクを減らせる
新社会人になるタイミングで生命保険へ入るメリットに、貯蓄が少なく経済的なリスクを軽減できる点も挙げられます。
新卒で働き始めたばかりの頃は、まだ十分な貯金がないケースも珍しくありません。
貯金の少ない状態で突然の病気やケガによって医療費がかかると、家計に大きな影響を及ぼす可能性があります。
リスクへ備えて医療保険に入っておけば、手元にお金がなくて治療費が払えない事態を防げます。
貯蓄が少ないうちは、万が一に備えて必要最低限の医療保障を備えておくと安心です。
保険の選択肢が広くなる
新卒社会人の若くて健康であれば、保険を選ぶ際に多くの選択肢から検討できます。
年齢を重ねるにつれ、健康診断で異常が見つかる場合や持病の治療が必要になる可能性も否定できません。
健康上の問題があると、保険へ加入する際に条件が付けられたり、加入自体を断られたりする場合もあります。
体調を崩してからでは保険の選択肢が限られる場合もあるため、注意が必要です。
健康な状態で無理なく加入できる保険を検討しておくと、将来の安心につながるでしょう。
新卒社会人が生命保険に入るデメリット
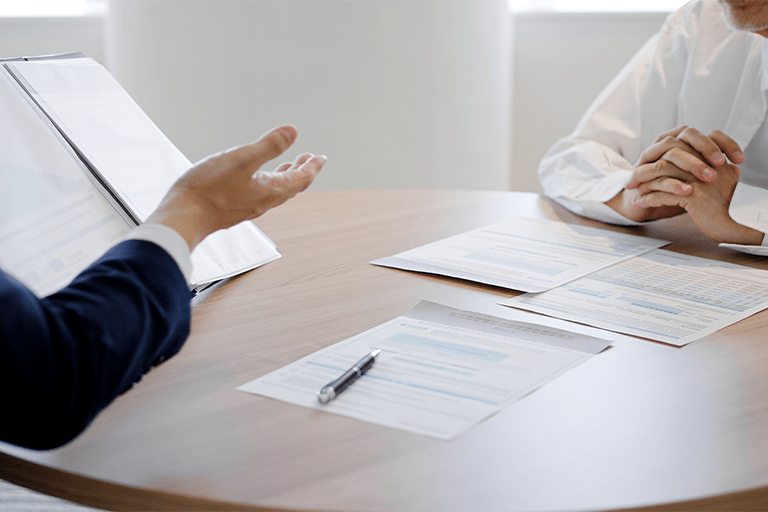
新卒社会人が生命保険に入る場合、いくつかの注意点があります。
毎月の保険料の支払いで経済的な負担となる可能性や、早期解約によって損失が出る可能性が挙げられます。
ここからは新卒社会人が生命保険に入るデメリットを詳しく見ていきましょう。
一定の保険料を支払う必要がある
保険に入る場合、月ごとや年ごとに一定の保険料を支払う必要があるのがデメリットになります。
初任給の中から保険料を出すのは負担に感じる方もいるでしょう。
収入に合わせて無理のない保険料の上限を決めて、検討しなければいけません。
勤務先から案内される保険商品は、あらかじめ内容がセットになっている場合が多く、自分には不要な保障まで含まれているケースもあります。
自分にとって本当に必要な保障内容を見極め、保険料を払いすぎないよう注意しましょう。
加入してすぐに解約すると損をする場合がある
終身保険や個人年金保険といった貯蓄型の保険商品には、解約時に返戻金が支払われます。
返戻金は契約してからの年数などをもとに算出されるため、一般的には加入期間が長いほど多く受け取れる傾向があります。
ただし契約して間もないうちに解約すると、支払った保険料よりも返ってくる金額が少なくなる場合が多いため、注意しましょう。
新卒20代の若いうちに検討するべき保険の種類と選び方
生命保険にはいくつかの種類がありますが、新卒社会人にとって今すぐ必要なものと、いらない種類もあります。
ここでは「生命保険は新卒社会人にいらないのか」と的確に判断できるよう、優先して検討すべき保険と、選び方のポイントを見ていきましょう。
必要性が高い保険
新卒社会人に必要性が高い保険は、以下のとおりです。
- 医療保険
- 就業不能保険
- 個人年金保険や終身保険
医療保険は、入院や手術の費用をカバーする基本的な保険で、若くても必要性は高くなります。
がん保険のように、がんに特化したタイプもあります。
就業不能保険は、病気やケガで長期働けなくなった場合の生活費をサポートする保険で、自営業やフリーランスの方におすすめです。
個人年金保険や終身保険は、保障と同時に老後資金の準備もできる貯蓄型です。
一般的に、早く加入するほど運用のメリットが大きくなります。
自分に合った保障を選び、無理のない範囲で検討する姿勢が大切です。
いらない保険
新卒社会人のまだいらない保険は、以下のとおりです。
- 高額な死亡保険
- 介護保険
- 学資保険
現在のライフステージに合っていない保険は、無理に加入する必要はありません。
高額な死亡保険は独身で家族を養っていない場合は基本的に不要なケースが大半です。
必要だとしても葬儀費用程度の最低限の保障で十分です。
介護保険は、高齢期のリスクに備えるものになるため、介護が必要な可能性の低い20代では優先度が下がります。
同様に、学資保険のように子ども向けの保険も、まだ子どもがいない段階では必要はありません。
結婚や出産など、ライフイベントに合わせて検討しましょう。
新卒社会人向けの生命保険の選び方
新卒社会人の生命保険の選び方は、以下があげられます。
- できるだけ保険料が安いものを選ぶ
- 必要な保障を見極める
- 将来的に資金形成ができるかどうか
新卒は収入が限られているため、毎月の保険料はなるべく低く抑えるのが基本です。
同じ保障内容でも、保険会社やプランによって料金に差があるため、複数の保険を比較して検討しましょう。
医療・死亡・就業不能などの種類がありますが、ライフスタイルや家族構成をふまえ、必要な保障のみを選ぶようにしましょう。
生命保険の中には、保障だけでなく「積立」や「貯蓄」の機能がある商品もあります。
老後資金や大きな出費に備えて、若いうちからコツコツお金を貯めたい方は、資産運用型の保険選びも1つの方法です。
いらないかどうか迷った時はプロに相談してみるのもおすすめ

社会人として働き始めると、けが・病気・収入の途絶などのリスクへの備えが気になる方も多いでしょう。
ただし、生命保険の仕組みは複雑な点も多く「自分に本当に合っているのか、いらないか」と悩んでしまうかもしれません。
特に新卒のタイミングでは、はじめて生命保険を真剣に考える方がほとんどで、不安や疑問を抱くのは当然です。
「保険のぷろ」の無料保険相談では、保険やお金に関する資格を持つアドバイザーが多数在籍しています。
専門家へ相談すると「いらない」と感じる無駄な保障を避け、自分にぴったりの保険を見つける助けになります。
記事まとめ

新卒社会人にとって生命保険はいらないかの判断は難しいのですが、基本的には公的保険や勤務先の保障があるため、必ずしも加入する必要はありません。
ただし若いうちに加入すると、保険料を抑えられたり、貯蓄が少ないリスクに備えたりできるメリットもあります。
もし迷った場合は無料の保険相談窓口を利用すると、自分に最適な保障内容を見つけるサポートが得られます。
必要な保障だけを選び、将来的に資産形成できる商品を選びましょう。