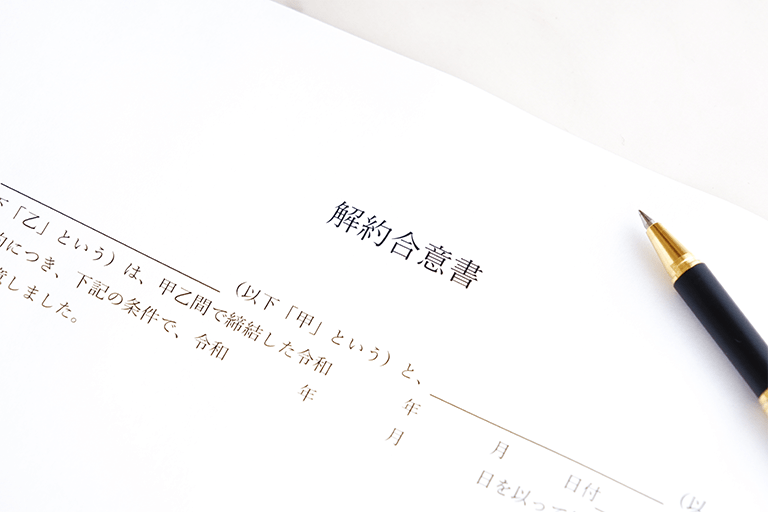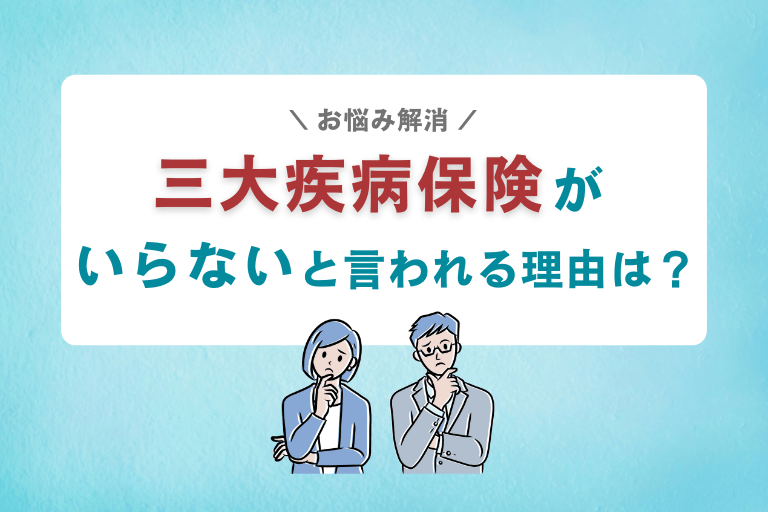生命保険金は相続放棄すると受け取れない?受け取る条件や注意点を解説
相続対策として生命保険へ加入したものの「相続放棄した場合に死亡保険金を受け取れるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
生命保険は相続対策として利用できますが、契約内容によっては相続放棄した場合に保険金を受け取れないケースもあるため注意が必要です。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、相続放棄した場合に死亡保険金の取り扱いがどうなるのかについて解説します。
相続対策で生命保険に加入している方、相続放棄を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
基本的に相続放棄しても生命保険の死亡保険金は受け取れる

結論から申し上げますと、相続放棄した場合でも、生命保険の死亡保険金は受け取れます。
亡くなった方(被保険者)が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産(※)」として受取人の固有財産とみなされるためです。
※本来の相続財産ではなく死亡によって権利が生じる財産
生命保険は、相続を放棄した場合でも受け取れる唯一の財産です。
何らかの理由で相続放棄を検討するケースでも、特定の方へ資産を残せる点は生命保険ならではの特徴と言えるでしょう。
相続放棄すべき方とは?
相続放棄すべきなのは、主に以下の状況にある方です。
- プラス財産よりマイナス財産が多い場合(相続により負債を抱える方)
- 亡くなった方が連帯保証人になっていた(相続により連帯保証となる方)
- 相続人の間でトラブルが生じている(相続争いに巻き込まれたくない方)
上記のとおり相続によって「マイナスの財産を抱える」または「トラブルに巻き込まれる」などのケースでは、相続放棄を検討すべきでしょう。
ただし「借金に責任を感じる」「すべての財産を相続放棄するのは気が引ける」と考える方は、相続放棄せずに限定承認する方法もあります。
例えば亡くなった方に預金が1,000万円、借金が1,500万円あれば、限定承認では預金1,000万円と借金のうち1,000万円を相続します。
限定承認した場合は生命保険の死亡保険金は受け取れる?
限定承認した場合でも、生命保険の死亡保険金を受け取れます。
相続放棄と同様に、被保険者が保険料を負担していた生命保険金は、受取人の固有財産とみなされるためです。
また生命保険の死亡保険金は受取人の固有財産であるため、被相続人(亡くなった方)の借金返済に充てる必要がありません。
例えば以下のケースで単純承認すると、借金返済の義務を負うのは預金額2,000万円までです。
生命保険金2,000万円は、借金の返済に充てる必要はありません。
- 預金:2,000万円
- 生命保険:2,000万円
- 借金:4,000万円
ただし相続放棄と限定承認のどちらを選ぶべきかは資産と負債の状況や、他の相続人との関係などさまざまな要素により異なります。
どちらを選ぶべきか判断がつかない場合は、弁護士や税理士など専門家に相談すると良いでしょう。
相続放棄で死亡保険金を受け取れないパターンとは
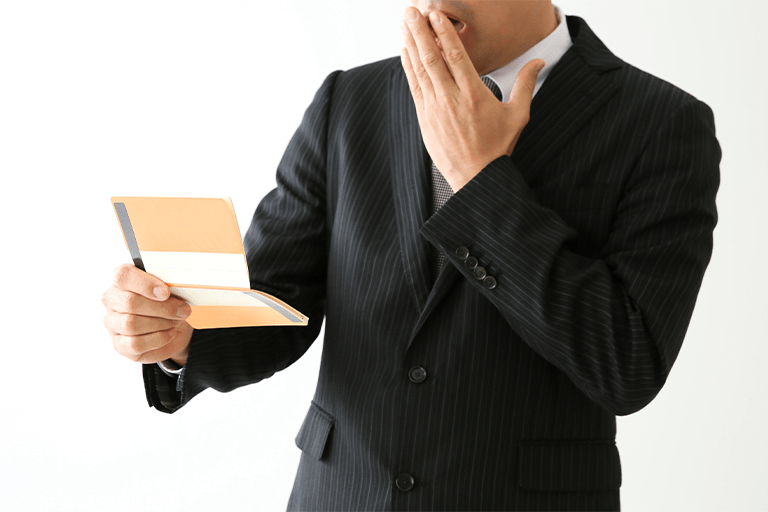
生命保険の死亡保険金には、相続放棄した場合に例外として受け取れないパターンがあります。
相続対策として生命保険の利用を検討している方は、どのようなパターンが該当するか知っておく必要があるでしょう。
ここでは、相続放棄した場合に生命保険の死亡保険金を受け取れないパターンについて解説します。
「亡くなった人=受取人」の保険金は受け取れない
相続を放棄した方は「亡くなった人=受取人」の保険金は受け取れません。
「亡くなった人=受取人」の契約では、保険金が被相続人(亡くなった方)の相続財産とされ「みなし相続財産」に該当しないためです(※)。
※相続放棄した場合に受け取りできるのは「みなし相続財産」に該当する場合のみ
- 死亡保険の解約返戻金(生前に解約した場合)
- 医療保険の入院給付金・手術給付金(死亡時点で未請求のもの)
上記保険金は相続財産として相続人(相続放棄していない方)が受け取ります。
受取人の指定がなく、保険約款の内容によって決まる場合
受取人の指定がなく、受取人が保険約款の内容によって決まる場合も、相続放棄した方は死亡保険金を受け取れません。
受取人が指定されていない保険契約では、約款により「法定相続人を受取人」としている保険会社がほとんどであるためです。
例えば以下のケースの場合、受取人指定のない死亡保険契約では、相続放棄したAは生命保険金を受け取れずに、BとCが均等に受け取ります。
- 法定相続人A : 相続放棄予定
- 法定相続人B : 相続放棄せず
- 法定相続人C : 相続放棄せず
もしAに生命保険金を受け取らせたいのであれば、契約変更によりAを受取人に指定する必要があります。
【要注意】生命保険の保険金受け取りにかかる税金について
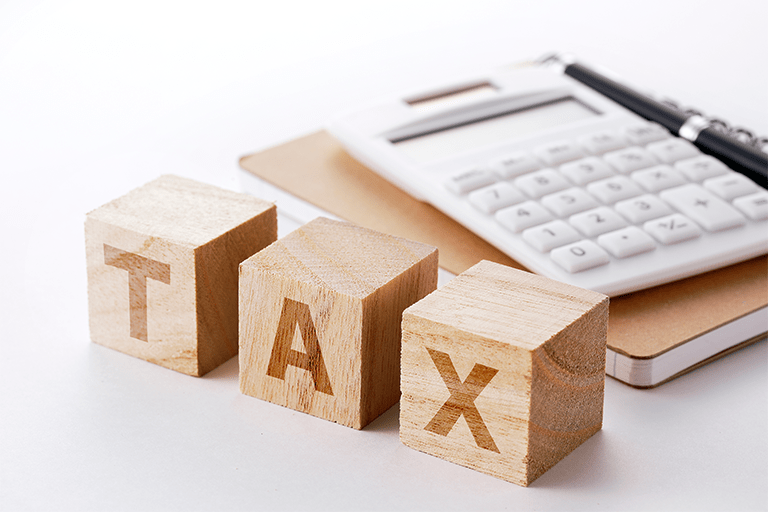
生命保険の保険金にかかる税金は、契約内容や受け取り方によって異なります。
何も知らずに受け取ると税負担が大きくなったり、思わぬペナルティが課されたりする場合もあるため注意が必要です。
ここでは、生命保険金の受け取りにかかる税金の種類と、注意すべきポイントを解説します。
相続放棄すると生命保険の非課税枠を使えない
相続放棄すると、放棄した方は生命保険の非課税枠を利用できず、相続税負担が大きくなる可能性があります。
生命保険の非課税枠は法定相続人を対象としており、相続放棄した方は「はじめから相続人でなかったもの」とみなされるためです。
生命保険の非課税枠=500万円 × 法定相続人数
例えば法定相続人が5人で保険金を受け取るケースでは、2,500万円が非課税扱いとなります。
生命保険の非課税枠=500万円 × 5人=2,500万円
相続放棄はマイナスの財産が多い場合に検討すべき制度ですが、非課税枠を考慮すると必ずしも有利なケースばかりと言えない点に注意が必要です。
贈与税や所得税がかかることも
生命保険金は、保険契約者(保険料負担者)と受取人の組み合わせによって、相続税ではなく贈与税や所得税がかかるケースもあります。
被保険者(保険対象者)以外の方が保険料を負担していた場合、生命保険金は贈与財産または所得(一時所得)とみなされるためです。
例えば夫、配偶者、子どもの3人家族では、契約者(保険料負担者)と受取人の組み合わせで以下のとおり税金の種類が異なります。
生命保険金にかかる税金の種類
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 配偶者または子ども | 相続税 |
| 配偶者または子ども | 夫 | 配偶者または子ども | 所得税 |
| 夫・配偶者・子ども以外の者 | 夫 | 配偶者または子ども | 贈与税 |
生命保険は、契約者と受取人の組み合わせで税金の種類や税率が異なるため、契約内容を慎重に判断する必要があります。
相続税がかかる場合は10ヶ月以内に申告・納税が必要
生命保険金を含め相続税がかかる場合は、10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要になります。
期限までに申告・納税が行われないと延滞税がかかるため注意が必要です。
相続税は、相続財産の合計額が以下の基礎控除額を上回る場合にかかります。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例えば亡くなった方に配偶者と3人の子どもがいるケースでは、基礎控除額5,400万円を超えると相続税の課税対象になります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円
相続税の申告には「誰がどの資産を受け取るか」を話し合う遺産分割協議や、必要に応じて相続放棄や限定承認の手続きが必要です。
相続が発生した時点で、早めに相続税申告の準備を始める必要があるでしょう。
記事まとめ
生命保険は相続税の非課税枠を利用できるため、相続税対策に活用できます。
また相続放棄しても保険金を受け取れるため、特定の親族へ資産を残したい方におすすめです。
ただし生命保険は契約内容によって、相続放棄した方が保険金を受け取れないケースもあります。
遺族へ確実に保険金を残すためにも、まずは保険会社や保険代理店などへ相談すると良いでしょう。