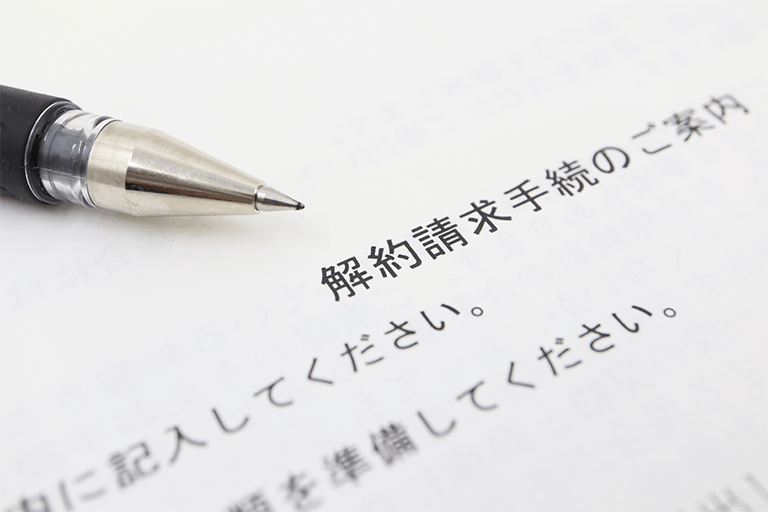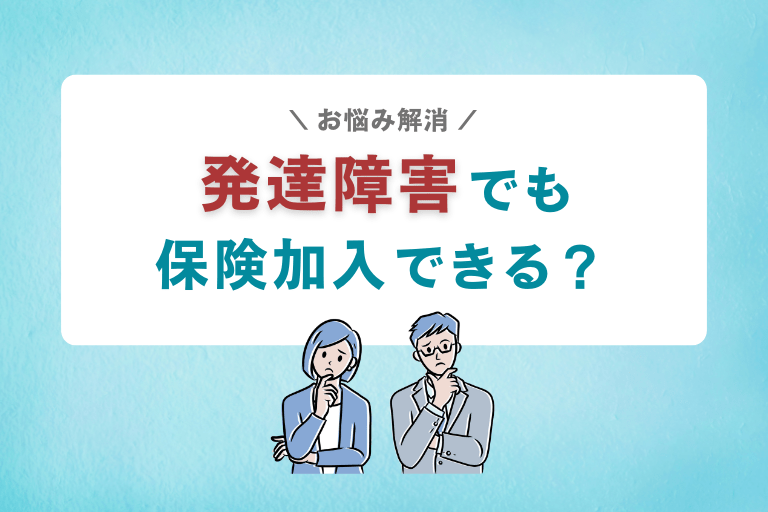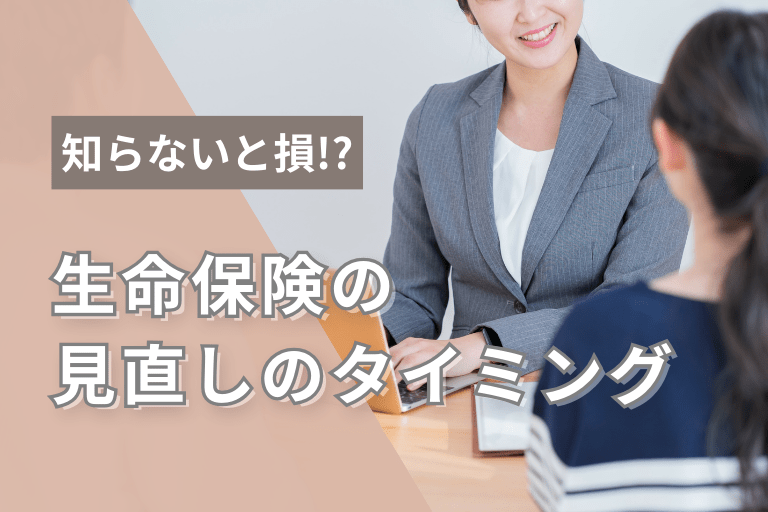旦那が死亡保険に加入していないリスクとは?加入を勧める際のポイントも紹介
「旦那に死亡保険の加入を勧めたい」「死亡保険に入ってもらいたい」
上記のように、旦那に死亡保険の加入を勧めたいと考えている方もいるでしょう。
旦那が死亡保険に加入していないと、経済的に困窮する可能性があります。
今回は無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、旦那が死亡保険に入っていないと起こり得るリスクについてわかりやすく解説します。
死亡保険に加入するメリットや、旦那に死亡保険の加入を勧めるポイントも解説しているため、死亡保険の加入を検討している方は、ぜひご覧ください。
旦那が死亡保険に入ってないことの5つのリスク

旦那が死亡保険に加入していないと、生活費や子どもの教育費が確保できないリスクが生じます。
以下では、旦那が死亡保険に入っていないと起こり得るリスクを具体的に5つ紹介します。
生活費が不足し、家計が厳しくなる
旦那が収入の柱となっている場合は、死亡保険に加入していないと、家計が厳しくなる可能性もあります。
遺族年金や公的な保障制度によって一定の保証は受けられますが、今まで通りの生活水準維持は難しくなるでしょう。
予期せぬ支出が重なれば、あっという間に貯蓄も底をつきてしまう可能性もあります。
死亡保険に加入していれば、旦那の万が一の際にまとまった保険金が支払われ、当面の生活費を確保できます。
住宅ローンの支払いが困難になる
マイホームを購入している家庭は、住宅ローンの支払いが困難になるケースもあります。
一般的にマイホームを購入する際は「団体信用生命保険(団信)」と呼ばれる保険に加入します。
団体信用生命保険とは、旦那が亡くなった際に、住宅ローンの残債が弁済される保険です。
しかし、団信に加入していない場合や、住宅ローン以外の借入がある方は、残された家族が毎月のローン支払いを継続しなくてはなりません。
住み慣れた家を手放さなくてはならないうえ、新たな住居を探すための費用も必要になります。
子どもの教育費が確保できなくなる
子どもの教育費が確保できなくなる点も、旦那が死亡保険に加入していない場合のリスクとしてあげられます。
教育費は小学校から中学校、大学など年齢が高くなるほど、必要な費用は増していきます。
たとえ、学資保険に加入している場合でも、学資保険の金額だけで全ての教育費を賄えるとは限りません。

死亡保険に加入していれば、保険金をお子様の教育資金に充てられる可能性があります。
葬儀費用の負担が大きくなる
旦那が死亡保険に加入していないと、葬儀費用の負担が大きくなります。
葬儀の規模や内容によって大きく異なりますが、数百万円単位の費用が必要になるケースも珍しくありません。
突然の出費となるため、貯蓄が十分にない場合、残された家族にとって大きな経済的な負担になります。
香典だけで全額をカバーするのは難しいでしょう。
死亡保険に加入していれば、保険金を葬儀費用に充てられ、突然の出費でも経済的な負担を抑えられます。
相続トラブルが発生する可能性も
旦那が死亡保険に加入していないと、相続トラブルが発生する可能性もあります。
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象とはなりません。
遺産分割とは、法律で決められた相続人が、財産の分け方を決める手続きを指します。
しかし、死亡保険に加入しておらず、預貯金のような遺産が少ない場合、遺産分割を巡って親族間でトラブルが発生するケースもあります。
不動産や土地など分割しにくい財産が多いと、調整は複雑になりやすい傾向にあるため、注意が必要です。
死亡保険に加入するメリットはある?

死亡保険に加入していると、残された家族の生活費を確保できたり、税金負担の軽減につながったりなど、メリットが得られます。
死亡保険の加入を検討している方は、加入しておくメリットも詳しく理解しておきましょう。
万が一の時に残された家族の生活費を確保できる
死亡保険に加入していると、万が一の時に残された家族の生活費を確保できます。
死亡保険によりまとまった保険金が支給され、生活費を確保し、将来の生活設計を立て直すための経済的な余裕が生まれます。
万が一の際に支払われる保険金の額は、商品や掛け金によって異なるため、一概にはいえません。
家族構成や収入、将来設計などを考慮し、保険金の額を検討しましょう。
税負担の軽減につながる(生命保険料控除)
生命保険料は、所得控除の対象となるため、税負担の軽減にもつながります。
死亡保険が所得控除の対象になる制度は「生命保険料控除」と呼ばれています。生命保険料控除は、所得税や住民税の負担を軽減する効果があるのが特徴です。
控除額は、保険の種類や加入時期によって異なりますが、年間で数万円の節税になる場合もあります。
死亡保険は保険料を支払い、万が一の備えができるだけでなく、税金も抑えられるのは大きなメリットといえます。
生命保険料控除を利用する際は、年末調整や確定申告で手続きをする必要がある点に留意しておきましょう。
貯蓄性のある死亡保険なら子どもの教育費や老後資金にも備えられる
満期金や解約返戻金のある貯蓄型の死亡保険は、将来に備えられるのもメリットです。
例えば、学資保険の代わりに、満期を迎える時期にお子様の進学時期に合わせると、保険金を教育資金として利用できます。
保険金を老後資金の一部として積み立てておくのも可能です。
ただし、貯蓄型の保険は、掛け捨て型に比べて保険料が高くなる傾向があります。
保障内容や貯蓄性以外にも、経済的な負担を踏まえ、自身にあった保険商品を選びましょう。
未加入の旦那に死亡保険を勧める際のポイント

死亡保険未加入の旦那に加入を勧める際は、ライフプランを絡めて相談するのがおすすめです。
ただし、死亡保険加入を押し付けるのではなく、お互いが納得して加入できるよう勧めるのが大切です。
ここからは、死亡保険未加入の旦那に、死亡保険を勧める際のポイントを4つ紹介します。
ライフプランを絡めて相談する
死亡保険の話を持ち出す際は、長期的なライフプランを共有しながら相談するのがおすすめです。
まず教育費や住宅ローンの返済計画、老後の生活設計など、将来必要となる資金を話し合います。
話し合いの過程で「万が一の際、ライフプランにどのような影響が出るのか」「誰が経済的な負担を担うのか」と死亡保険の必要性を説明しましょう。
ライフプランと交えて死亡保険の説明をすると、保険の必要性やメリットを旦那に理解してもらいやすくなります。
「あなたのため」ではなく「家族のため」と伝える
死亡保険は、自身ではなく、残された家族のための備えである点も伝えておくべきポイントです。
「あなたのため」よりも「家族のため」の視点から話すと、死亡保険の加入に前向きになってもらえる可能性があります。
「子どものために死亡保険に加入してほしい」「一緒に死亡保険に加入しよう」と、家族のためである点を伝えましょう。
老後資金の備えにもなることも伝える
死亡保険の中には、掛け捨て型だけでなく貯蓄性のあるタイプが、老後資金の備えになる点も旦那に伝えましょう。
満期保険金や解約返戻金があるタイプの保険であれば、老後資金の一部として一部を積み立てできます。
旦那が老後に不安を抱いている場合は、万が一に備えながら貯蓄できる保険は、魅力と感じる方も多いでしょう。
夫婦揃って無料相談窓口を利用する
夫婦だけでの話し合いが難しい場合は、夫婦で無料相談窓口を利用するのがおすすめです。
保険の専門家に客観的な情報やアドバイスを受けると、死亡保険の必要性や適切な保障額をより詳しく理解しやすくなります。
また、夫婦揃って相談すると、お互いの認識をすり合わせ、納得のいく結論を出しやすくなるのが特徴です。
記事まとめ
死亡保険に加入していないと、生活費の確保が難しくなったり、住宅ローンの支払いが困難になったりするリスクもあります。
万が一の際に備えるためには、死亡保険に加入を検討しましょう。
死亡保険に加入していれば、残された家族の生活費を確保できるうえ、税軽減にもつながります。
死亡保険加入の話を持ち出す際は、ライフプランを絡めて相談すると、納得してもらいやすい傾向にあります。
また、夫婦だけで相談するのが難しい場合は、保険の専門家に相談するのがおすすめです。