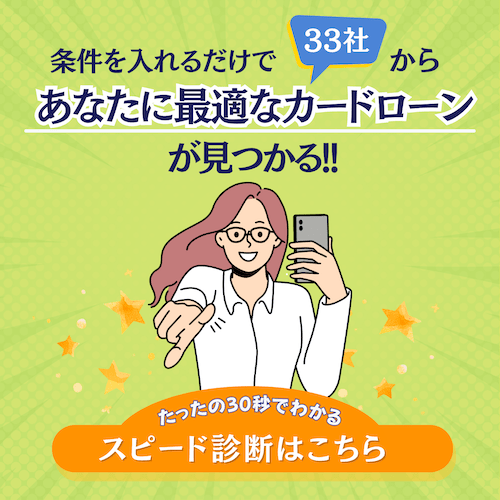消費者金融で自己破産した後の影響と再借入までの必要期間を解説
消費者金融の返済が難しくなり自己破産を考えている方にとって、「その後の生活はどうなるのか?」
という不安は大きいでしょう。
自己破産をすると借金の返済義務が免除される一方で、財産の処分や信用情報への影響など、さまざまな制約が発生します。
特に、一定期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなるため経済的な立て直しは欠かせません。
本記事では、自己破産後の影響や再び借入できるまでの期間について解説します。
また、自己破産後も借入できる可能性があるカードローンもまとめているので参考にしてください。
自己破産とは消費者金融などの返済を免除する手続き

自己破産とは、裁判所の許可を得ることで借金の返済義務を免除してもらう法的手続きです。
消費者金融などからの借金の返済が困難になった場合、「自己破産」という法的手続きを利用することで、返済の義務を免れることができます。
しかし、自己破産には一定の条件や手続きが必要であり、すべての借金が無条件で免除されるわけではありません。
自己破産の条件
自己破産の条件は以下のとおりです。
- 借金の返済が継続的に不可能な状態である
- 非免責債権の他にも借金がある
- 免責不許可事由に該当していない
借金の返済が継続的に不可能な状態である
自己破産をするためには、借金の返済が継続的に不可能な状態であることが必要です。
これは単に「今月の返済ができない」といった一時的な支払困難ではなく、将来的にも返済の見込みが立たない状況を指します。
具体的には「収入」「資産の有無」「生活費のバランス」などを裁判所が総合的に判断し、支払不能かどうかを決定する仕組みです。
非免責債権の他にも借金がある
自己破産をしても、すべての借金が免除されるわけではありません。
免除されない借金を「非免責債権」といい、以下のようなもの挙げられます。
- 税金
- 国民健康保険料
- 養育費
- 交通事故の損害賠償
- 罰金 など
これらの借金は自己破産をしても支払い義務が残るため、自己破産をする意味が薄れてしまいます。
免責不許可事由に該当していない
自己破産は「借金の免除」という大きな救済措置ですが、不適切な借り方や使い方をしていた場合は免責が認められない可能性があります。
基準となるのが「免責不許可事由」であり、具体的には以下のような行為が該当します。
- 破産直前に財産を隠したり、親族に名義を変更したりする
- 一部の債権者(親族や友人など)にだけ返済する
- ギャンブルや浪費が原因で借金を作る
- 収入を偽って借入をする
- 債権者一覧を偽る、裁判所の調査に協力しない
- 過去7年以内に自己破産している など
ただし、これらの行為に該当した場合でも裁判所の判断で反省の態度や経済状況が考慮され、免責が許可されるケースもあります。
自己破産の種類は3つ
自己破産は、大きく分けて「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」の3つに分類されます。
どの手続きを適用するかは、申立人の財産の有無や借金の内容によって異なります。
同時廃止
同時廃止とは、破産手続きと同時に事件が終了する手続きのことです。
自己破産の中で最も簡単な手続きであり、財産がほとんどない方に適用されます。
裁判所が破産手続きを開始すると同時に破産手続き自体を終了するため、破産管財人(破産手続きを管理する専門家)の選任も不要で、費用や時間が最もかかりません。
管財事件
管財事件とは、家や車などの一定以上の財産を持っている場合や、免責不許可事由がある場合に適用される手続きです。
この場合は破産管財人が選任され、財産の処分や債権者への配当が行われます。
少額管財事件
少額管財事件とは管財事件の簡易版のような手続きであり、財産が少額で破産管財人の調査が必要な場合に適用されます。
通常の管財事件よりも手続きが早く、費用も抑えられるのが特徴です。
自己破産の手続き方法
自己破産の手続きの方法は、主に以下のとおりです。
- 弁護士に相談し、手続きを依頼する
- 債権者に対し、弁護士が介入したことを通知する
- 必要な申請書類を準備し、提出する
- 裁判所に申し立てを行う
- 裁判所の審尋(面談)を受ける
- 破産手続きの開始が決定される
- 必要に応じて財産の処分が行われる
- 免責審尋を受ける
- 免責が許可され、借金の返済義務がなくなる
自己破産を進めるには弁護士に相談し、手続きを依頼することが一般的です。
その後、債権者への通知や必要書類の準備を進め、裁判所へ申し立てを行います。
消費者金融で自己破産をするとどうなる?
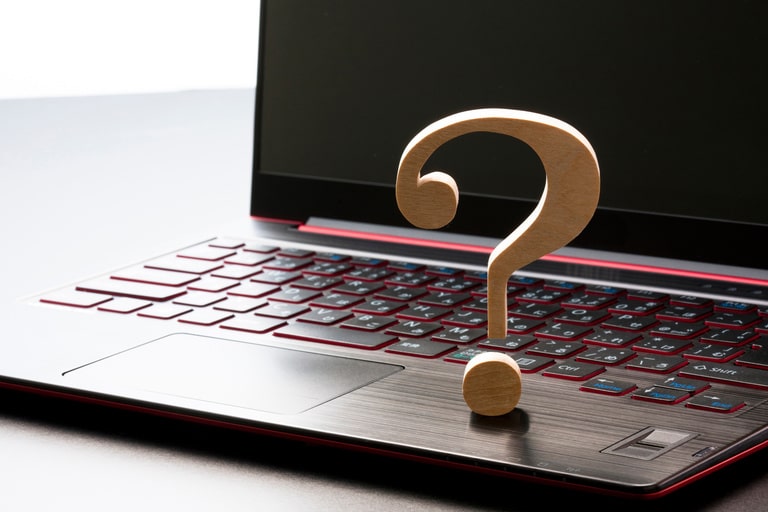
ここでは、自己破産後に生じる具体的な影響について解説します。
ほぼ全ての財産が処分になる
自己破産をすると債権者への公平な返済のために、基本的に所有する財産のほとんどが処分されます。
例えば、預貯金や不動産、車などの高価な資産は原則として換価処分され、借金の返済に充てられます。
ただし、生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金や家電製品など)は手元に残せるため、すべてを失うわけではありません。
官報に掲載される
自己破産すると、破産者の情報が国の発行する「官報」に掲載されます。
官報とは政府が発行する公的な文書で、破産手続きが行われたことを社会に知らせる役割を持っています。
一般の方が官報を見る機会はほとんどありませんが、金融機関や一部の業者は官報をチェックしているため、特定のサービスを利用する際に影響を受ける可能性があります。
職業や資格が一定期間制限される
自己破産をすると、弁護士や税理士、宅地建物取引士などの一部の職業や資格に制限がかかります。
ただし、破産手続きが完了して免責許可が下りれば再び資格を取得できるため、永久的に仕事ができなくなるわけではありません。
引っ越しや旅行が一定期間制限される
自己破産が「管財事件」として進められる場合、財産調査が完了するまで裁判所の許可なしに引っ越しや長期間の旅行をすることは不可能です。
これは、破産者が無断で移動することで破産管財人による財産の管理や換価処分に支障をきたす可能性があるためです。
ローン契約やクレジットカードの利用ができなくなる
自己破産をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録され、一定期間ローン契約やクレジットカードの利用ができなくなります。
ブラックリスト入りによる主な影響は以下のとおりです。
- クレジットカードの新規発行や利用ができない
- 銀行や消費者金融からの借入れができない
- スマートフォンや家電の分割払い契約が組めない
- 賃貸物件の審査で不利になる可能性が高い
自己破産後、5~7年は借入が難しくなる

信用情報機関は以下の3つがあり、自己破産した場合の事故情報は5年~7年程度登録されます。
以下の表は、信用情報機関ごとの事故情報登録期間の目安をまとめたものです。
| 信用情報機関 | 事故情報の登録期間 |
|---|---|
| CIC | 免責決定後、約5年間登録される |
| JICC | 破産申立後、約5年間登録される |
| KSC | 破産手続開始決定後、約7年間登録される |
返済免除した消費者金融の再契約はさらに厳しい
自己破産で借金を免除してもらった消費者金融では、今後の契約が極めて難しくなります。
これは「社内ブラック」と呼ばれるもので、信用情報機関のブラックリストとは別に各金融機関が独自に管理している情報に記録されるためです。
例えばアコムからの借入を返済できず自己破産で解決すると、社内ブラックの情報が残る限り、アコムや三菱UFJ系列の会社から借り入れをすることが難しくなります。
自己破産後も借入できる消費者金融

自己破産をすると多くの金融機関でローン契約が難しくなりますが、一部の中小消費者金融では「在籍確認なし」といった独自の審査基準を設けており、大手よりも柔軟な場合があります。
そのため、ブラックリスト状態でも借入の可能性がある消費者金融としては以下のような業者が挙げられます。
- いつも
- フタバ
- アムザ
ただし、これらの業者でも確実に借りられるわけではなく、自己破産後の経過期間や現在の収入状況などが審査の重要なポイントです。

まとめ

自己破産は消費者金融などの借金返済が困難な場合に利用できる法的手続きですが、財産の処分や信用情報の登録など、さまざまな制限が発生します。
特に、ローン契約やクレジットカードの利用ができなくなり、再び借入が可能になるまでに5~7年かかるのが一般的です。
ただし、一部の中小消費者金融では自己破産後でも審査の通過が可能な場合があります。
自己破産を検討する際はメリットとデメリットを十分に理解し、慎重に判断することが重要です。