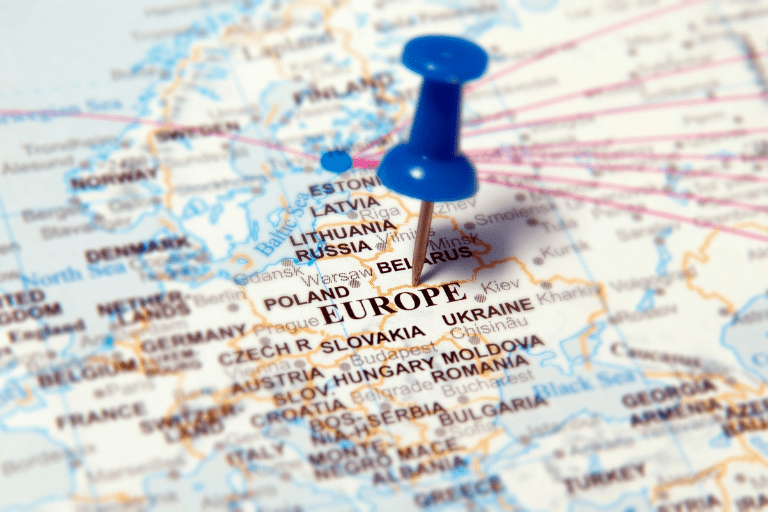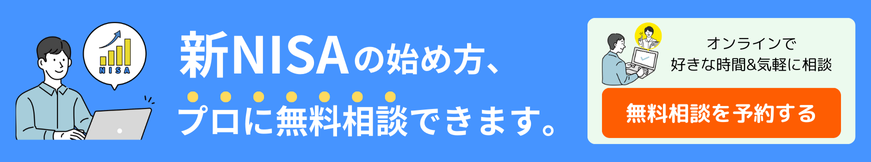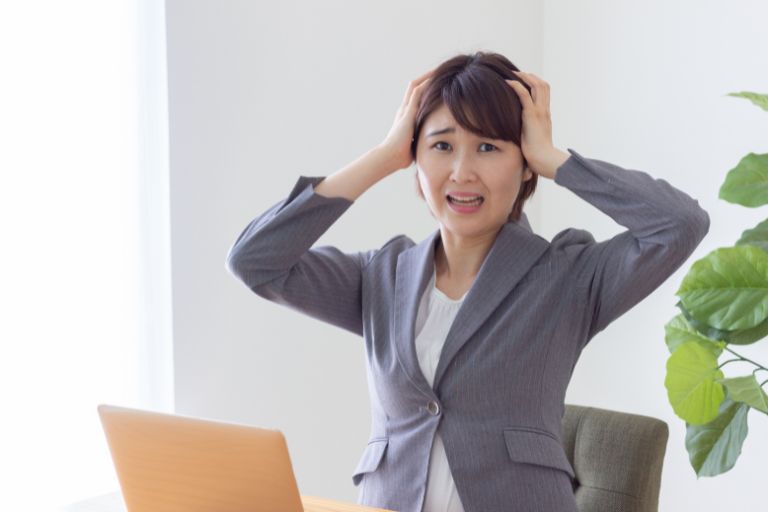
投資信託が持つリスクやデメリット、損せず資産運用するためのポイントを解説
投資信託は100円からの投資が可能で、多くの投資家にとって魅力的な資産運用の選択肢です。しかし、一部からは「投資信託はやめたほうがいい」という声もあります。
投資信託に限らず、どのような投資でも良い面と悪い面があります。「銀行や証券会社におすすめされた」「テレビやWebの広告でよく見るから」など、安易な理由で始めると痛い目を見るかもしれません。
投資信託で失敗しないためには、リスクやデメリットを理解し、適切な方法で運用することが大切です。また、運用資金や投資スタイルなど、自身の状況に合わせて運用する必要もあります。
この記事では、投資信託が持つリスクやデメリットを紹介するともに、投資信託が向いていない人の特徴や、損せず資産運用するためのポイントについて詳しく解説していきます。
「投資信託はやめとけ」と言われる理由

「投資信託はやめとけ」と言われるのは、以下のリスクやデメリットが主な要因です。
- 元本保証がないから
- 手数料などのコストが高いから
- 短期利益が期待できないから
- ファンド選びが難しいから
初心者でも始めやすい投資信託ですが、上記のように複数のリスク・デメリットがあります。逆に言えば、これらのリスクやデメリットを把握しておけば、損失を防ぐための対策や心構えも可能です。
それぞれ詳しく解説します。
元本保証がないから
投資信託は、投資家から集めた資金をプロのファンドマネージャーが運用する金融商品です。運用によって得られた利益は「分配金」として、投資家へ分配されます。
専門家に運用してもらえるため、素人があれこれ考えるより的確に運用できるのが強みですが、元本保証はありません。つまり、市場の急変や運用の失敗によって、資産価値が投資金額を割ってしまう恐れがあります。
「確実に儲かる」「絶対に損しない」という考えは危険であり、失っても構わない余剰資金で運用するようにしましょう。
なお、元本保証がある(もしくはそれに近い)金融商品としては、以下が挙げられます。
- 定期預金(金融機関ごとに元金1,000万円と利息まで保証)
- 国債、地方債、社債(元本保証ではないがリスクは低い)
ただし、元本保証がある金融商品は、投資信託と比べるとリターンが少なくなります。許容できるリスクを把握したうえで、なるべくリターンの高い金融商品を選ぶことが大切です。
手数料などのコストが高いから
投資信託には、購入時手数料や信託報酬(運用管理費用)など、さまざまなコストが伴います。これらのコストは運用成果から差し引かれるため、実際のリターンが減ってしまいます。
例えば、「毎月3万円を積み立てて、運用利回りが年7%、信託報酬が年1%」という条件でシミュレーションした場合、20年間で支払う信託報酬は約151万円です。
■月3万円の積み立てで年利7%の運用をしたときのシミュレーション
| 5年 | 10年 | 20年 | |
|---|---|---|---|
| 積立元本 | 180万円 | 360万円 | 720万円 |
| 積立元本+運用益(信託報酬控除前) | 207万円 | 497万円 | 1,475万円 |
| 信託報酬 | 4万円 | 22万円 | 151万円 |
| 積立元本+運用益(信託報酬控除後) | 202万円 | 474万円 | 1,324万円 |
シミュレーション参考::運用シミュレーター|楽天投信投資顧問株式会社
運用期間が長いほどコストも増大するため、長期投資の場合は信託報酬率の低いファンドを選ぶ必要があります。
短期利益が期待できないから
投資信託は基本的に長期投資向けであり、短期間での高リターンは期待できません。これは、投資信託の仕組みに理由があります。
投資信託は、投資家から集めた資金をさまざまな銘柄に分散投資しています。分散投資は、個々の銘柄に投資するよりリスクを抑えられる反面、得られるリターンも減ってしまう点がデメリットです。
例えば、2023年の騰落率(一定期間の値動きの割合)において、日経平均株価の企業全体に投資する「インデックスファンド225」と、そのなかでも年間トップの上昇率になった「神戸製鋼所」を比較すると、次のようになります。
| 始値(円) | 終値(円) | 騰落率(円) | |
|---|---|---|---|
| インデックスファンド225 | 30,378 | 39,869 | 31.2% |
| 神戸製鋼所 | 640.0 | 1,824.5 | 185% |
あくまで結果論ですが、2023年の1年間で見れば、リターンに6倍近い差があります。
「リスクを取ってでも短期で利益を稼ぎたい」という投資スタイルの場合、投資信託より個別株のほうが良い結果になる可能性があります。
ファンド選びが難しいから
市場には数多くの投資信託が存在し、それぞれに異なる運用方針、リスク、コスト構造があります。多くの選択肢から最適なファンドを見つけ出すのは、特に投資初心者にとっては困難な作業です。
適切なファンド選びに失敗すると、期待したリターンを得られないだけでなく、資産を減少させる可能性もあります。
目論見書や運用実績からファンドの特性を見極め、自身の投資目的やリスク許容度に見合ったファンドを選択するには、一定の知識と経験が必要です。こうしたスキルは一朝一夕では身につかず、勉強と経験を重ねる必要があります。
投資信託をやめた方が良い人の特徴
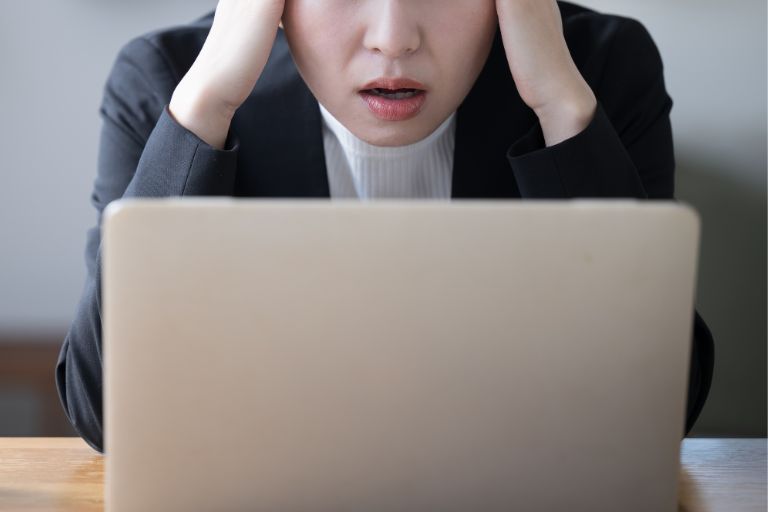
投資信託は初心者でも始めやすい反面、向き不向きもあります。特に、以下の特徴にあてはまる人は避けたほうがよいでしょう。
- 長期的な視点で考えるのが苦手
- 常に値動きが気になってしまう
- コストを最小まで減らしたい
それぞれ詳しく解説します。
長期的な視点で考えるのが苦手
投資信託の利益は、長期的な市場の成長に依存します。したがって、短期間での高リターンを期待している人や、一時的な値下がりに耐え切れず運用を途中でやめるような人は、あまり向いていません。
目先の損益や感情に流されず、5年、10年といった長いスパンで運用することが大切です。
常に値動きが気になってしまう
ファンドの価格は毎日変化するため、短期的な価格変動で神経質になりがちな人にはおすすめできません。市場の変化を気にしすぎると、不安で買い時・やめ時を見誤るなど、失敗する恐れがあります。
ポートフォリオ(資産構成)の定期的な見直しなども必要ですが、日々の値動きに一喜一憂しないよう、大きな視野を持って運用に取り組みましょう。
コストを最小まで減らしたい
先にも解説した通り、投資信託は運用に伴うさまざまなコストがかかります。資産運用のコストを極限まで削りたいなら、自分で個別株に直接投資したほうがよいでしょう。
ただし、信託投資のなかにも手数料が低いファンドはあります。むやみにコストを削るのではなく、トータルでどの程度のリターンを得られるか考えることが、資産運用では大切です。
リスクやデメリットだけじゃない!投資信託のメリットとは?

ここまで投資信託のリスクやデメリットを紹介しましたが、当然ながらメリットも存在します。悪い部分ばかりではなく、良い部分にも目を当てることが資産運用では重要です。
主な投資信託のメリットとしては、次の3つが挙げられます。
- 分散投資でリスクを抑えられる
- プロに運用を任せられる
- NISAのつみたて投資枠が使える
それぞれ詳しく見ていきましょう。
分散投資でリスクを抑えられる
先述のとおり、投資信託は集めた資金をさまざまな銘柄に分散して運用します。分散投資は、リターンが減る代わりに値下がりリスクも軽減できる点がメリットです。
例えば、銘柄Aが40%の下落になっても、銘柄Bと銘柄Cがそれぞれ25%の上昇になっていれば、トータルでは10%のプラスとなります(投資額が同じ場合)。
個人で分散投資をする場合、各銘柄の実績などを逐一調べる必要があり、非常に手間がかかります。一方、投資信託であれば1つのファンドを選ぶだけで数十から数千の銘柄に分散投資できるため、簡単にリスク軽減が可能です。
また、100円からの積立投資ができるので、時間的な分散投資につながる点もメリットです。常に一定の金額を積み立てて投資することで、安値のときに多く、高値のときに少なく購入することになり、買付の平均単価をフラットにできます。
プロに運用を任せられる
投資信託で実際に資産を運用するのは、高度な金融知識を持ったファンドマネージャーです。これにより、投資に関する深い知識や市場分析が不足している投資家でも、プロのスキルと経験を活かした運用を利用できます。
また、投資は資金が多いほど有利になり、市場での影響力も増します。投資信託の純資産額は数十億~数千億円規模なので、個人投資家より圧倒的に巨額の運用に参加可能です。
NISAのつみたて投資枠が使える
少額投資の非課税制度であるNISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがあり、それぞれ非課税となる年間投資枠が決まっています(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)。
これらは併用可能ですが、つみたて投資枠は金融庁が認めた一定の投資信託のみが対象で、個別株には適用できません。つまり、NISAの非課税枠を最大限活用するなら、投資信託の購入は欠かせないことになります。
つみたて投資枠を活用すれば、運用益に対して税金がかからなくなるため、より効率的に資産を増やせます。
ほかの投資方法との比較

投資には投資信託以外にもさまざまな選択肢があり、自分の目的や投資スタイルに合わせた方法を選ぶことが大切です。
投資信託とそれ以外の投資方法をおおまかに比較すると、次のようになります。
| 投資商品 | リターン | 信用リスク | 価格変動リスク | その他リスク | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 中程度 | 比較的低い | 比較的低い | 為替リスク・カントリーリスク(海外投資の場合) | 高い |
| 預金 | 低い | 非常に低い | なし | なし | 非常に高い |
| 株式 | 高い | 中程度 | 高い | 企業の業績に依存 | 高い |
| 外貨(FX) | 高い | 高い | 高い | 為替リスク | 高い |
| 債券 | 低い〜中程度 | 低い | 中程度 | 発行元の信用状況に依存 | 中程度 |
投資全体で見ると、投資信託はローリスク・ミドルリターンであり、比較的安定した利益が期待できる投資商品です。
「資産運用を始めたいけどリスクはなるべく取りたくない」という人なら、ぜひ投資信託を検討してみましょう。
こんな運用はやめとけ!購入前後の要注意ポイント

投資信託で損をしないためには、適切な運用方法が重要になります。主な注意点として、次に挙げるような運用は避けるようにしましょう。
- 目論見書や運用方針をチェックしない
- リスク許容度を超えたファンドを買う
- ひとつのファンドだけに集中する
- 購入してからほったらかしにする
これらを避ければ、投資信託で失敗するリスクを下げられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
目論見書や運用方針をチェックしない
投資信託を選択する際には、ファンドの目論見書や運用報告書をしっかりと読み込み、運用方針、リスク、手数料などを確認することが不可欠です。ファンドの特性や運用戦略を理解せずに投資を行うと、予期せぬリスクや損失が発生する可能性があります。
また、自身のリスク許容度に合わないファンドに投資してしまうと、市場の不況時に大きなストレスとなります。投資は精神面の安定も重要なので、後悔しないためにも情報収集と分析は徹底しましょう。
リスク許容度を超えたファンドを買う
過度にリスクの高いファンドに投資することは、市場の変動による損失のリスクも高めます。自分のリスク許容度を正確に把握し、それに見合ったファンドを選択することが重要です。
リスク許容度の測り方は人によりますが、年齢や性格を考慮すると良いでしょう。
年齢は、若い人ほど運用にかけられる期間が多いため損失をカバーしやすく、ひいてはリスクも取りやすくなります。一方、高齢で損失カバーできる期間が短いと、リスクよりも安定性のほうが重要になります。
性格については、購入したい銘柄が下落したとき、どこまでなら耐えられるかがポイントです。現状の-10%、-20%…と想像し、売りたくなるラインがあれば、そこが性格的なリスク許容度のボーダーラインとなります。
ひとつのファンドだけに集中する
投資信託は1つで分散投資できる点がメリットですが、それでもファンドごとに投資先の偏りがあります。そのため、なるべく複数のファンドに投資し、よりリスクを軽減することが大切です。
例えば、ファンドの分類として「国内株式型」というものがありますが、保有ファンドがこれ1つだけだと、日本経済が悪化したときに急落する恐れがあります。一方、同時に「海外株式型」や「海外債券型」のファンドも保有していれば、資産の減少を抑えられるかもしれません。
複数の異なる特性を持つファンドに分散投資し、より安定した運用成績を目指しましょう。
購入してからほったらかしにする
投資信託を購入した後、そのまま放置してしまうのは非常に危険です。
市場環境は常に変化しており、購入時に最適だった投資信託も、世界情勢などの影響で条件が悪くなる場合もあります。
また、自身の経済状況やライフステージの変化によっても、投資方針の見直しが必要になるかもしれません。例えば、退職や住宅購入などの大きなライフイベントの前後で、よりリスクの低い資産へシフトしたくなる可能性があります。
これらのリスクを防ぐためには、定期的なポートフォリオの見直しが大切です。その時々の状況に応じて、常に投資戦略を最適化させましょう。
記事まとめ

投資信託には、分散投資やプロの運用を利用できるといったメリットがある一方、元本保証がなかったり手数料があったりなどのデメリットも存在します。
しかし、こうしたメリット・デメリットはどの投資にも存在するため、いかに自分の投資目的やリスク許容度に合った選択をするかが重要です。
投資信託は少しずつ積み立ててコツコツ運用する方法が向いているため、「長期的にローリスクで資産運用をしたい」という人におすすめです。適切な投資判断とリスク管理で、資産形成を成功させましょう。